![]()
この本をすすめる本当の理由
『末期ガンは手をつくしてはいけない
ホスピス医が書いた「医療」ではなく「ケア」をすすめる本当の理由』
金重哲三(医学博士)著、中経出版
 ほとんどのガンに外科手術、薬物療法、X線照射が有効でないというのは、近藤誠が『がんは切ればなおるのか』(新潮社)で提起した問題である。この問題提起は医学界を含むさまざまな領域に大きなセンセーションを巻き起こし、その結果、アンサーソングならぬアンサー本が大量に出るなど、大きな議論を巻き起こすことになった。患者側である我々としてみれば、近藤誠の著書が説得力があるだけに、こういう議論は歓迎すべきことで、これを契機に真実を追求してほしいのだ。近藤誠のいうように「一般的にガンといわれているものは、治らないものと治るもの(ガンもどき)があって、外科手術で良好な結果が出ているのは切らなくても治るガンもどきだったに過ぎない」というのが正しいんだろうと、個人的には思う。
ほとんどのガンに外科手術、薬物療法、X線照射が有効でないというのは、近藤誠が『がんは切ればなおるのか』(新潮社)で提起した問題である。この問題提起は医学界を含むさまざまな領域に大きなセンセーションを巻き起こし、その結果、アンサーソングならぬアンサー本が大量に出るなど、大きな議論を巻き起こすことになった。患者側である我々としてみれば、近藤誠の著書が説得力があるだけに、こういう議論は歓迎すべきことで、これを契機に真実を追求してほしいのだ。近藤誠のいうように「一般的にガンといわれているものは、治らないものと治るもの(ガンもどき)があって、外科手術で良好な結果が出ているのは切らなくても治るガンもどきだったに過ぎない」というのが正しいんだろうと、個人的には思う。
そして、この本。
この本は、その議論をさらに一歩進めるものである。
末期ガンは何をやっても治らないのだから、無駄な治療で体を傷つけるのをやめて、死を受け入れるべきだというのが、その主張である。
つまり、「覚悟して捨て、感謝して逝く!」
いつまでも生き延びたいと思うのは「欲」だという。しかも末期ガンであれば、絶対にかなわない「欲」だ。このような欲を捨て去って「足るを知」り、平穏に死を迎えることこそ、本人、つまり患者にとって一番良いのだという。それがホスピス医として、大勢の患者を看取ってきた著者の主張だ。現場の人間の言葉だけに説得力がある。
末期ガンから死に至るまでの患者の体の変化も、具体的に紹介している。そうして、通常のガンの痛みであればモルヒネを使うことでかなりの程度抑えられるということも。さらに、管を体に入れたり、間違った治療を行ったりすることで、患者がどれだけ苦しめられ、尊厳を踏みにじられるかということも紹介している。しかも多くの場合、家族の意志でそのことが行われているという現実。
著者は、末期が近くなって体と心が衰弱していく過程を「経過が順調」と表現している。まさにコペルニクス的転回だ。
個人的には、病院に行けば医者の手で殺されることもあると思っているため病院は敬遠しているが、病院が万能だと思っている人も大勢いる。そのような人にこそ、ぜひこの本を読んでいただきたい。
最後に「悔いのない逝き方 十七箇条」という章があり、正しい死に方が示されている。しかしそれは、同時に生き方の哲学でもある。
![]()
マクドやめますか、それとも人間やめますか
『ハンバーガーに殺される 食肉処理事情とアルツハイマー病の大流行』
マレー・ウォルドマン&マージョリー・ラム著、熊井ひろ美訳、不空社
 プリオンで感染するとされるBSE(狂牛病)やクロイツフェルト・ヤコブ病とアルツハイマー病が実は同じものではないかという仮説を大胆に提示した画期的な書。
プリオンで感染するとされるBSE(狂牛病)やクロイツフェルト・ヤコブ病とアルツハイマー病が実は同じものではないかという仮説を大胆に提示した画期的な書。
アルツハイマー病に類似する症状が19世紀にはほとんど報告されていないこと(アルツハイマー博士によって同種の症状が初めて報告されたのが1906年)、一定年齢以上の死亡率はその間もあまり変わっておらず「長生きが増えたからアルツハイマー病が増えた」という議論に意味がないこと(平均寿命が延びているのは乳幼児の死亡率が減少しているためという)などを紹介しながら、アルツハイマー病が20世紀になって蔓延した新種の病気であると理路整然と説く。
アルツハイマー病とプリオン病の共通点は非常に多いという。著者は、アルツハイマー病が蔓延した(または蔓延していない)国々の状況を示して、その蔓延が牛肉の大量消費と軌を一にしていることをデータで示す。たとえば、日本では1960年以降出現している(牛肉の大量消費は第二次大戦後始まった)し、インドではアルツハイマー病がほとんど発生しない(宗教上の理由から牛肉はほとんど食べられない)。また、牛肉の大量一括処理(数頭の感染牛の肉を大量の食品にまき散らすことになる)の増加もアルツハイマー病の増加と軌を一にしているとする。
このようにして、アルツハイマー病が蔓延した原因は、BSEと同様、プリオンに感染した牛の部位を人が経口摂取したことではないかと結論づけている。
アルツハイマー病と(クロイツフェルト・ヤコブ病やBSEなどの)プリオン病は症状がかなり似ているにもかかわらず、患者が一定の症状(痴呆など)を見せた場合、その病名の診断(つまりアルツハイマー病であるかクロイツフェルト・ヤコブ病であるか)は問診で決まるという。現実的にはそれだけの差しかないのだ。
アルツハイマー病やプリオン病に限らず、病気の蔓延を防止する方法は、まずその発生のしくみを解明することだ。本書で述べられている説は、そのための第一歩として非常に有意義である。
さまざまな疑念に対してひとつひとつ丁寧に論証が進められるため、理解しやすく、ミステリーを読むようなスリリングさもある。BSEやクロイツフェルト・ヤコブ病についても、誰にでもわかるよう詳細に解説されている。400ページの大容量だが、ムダがなく、読む価値は十分にあると言える。一部翻訳文が読みづらいのが残念。
![]()
脂肪大国、アメリカ
『デブの帝国 いかにしてアメリカは肥満大国となったのか』
グレッグ・クライツァー著・竹迫仁子訳、バジリコ
 タイトルと装丁から、もっとおちゃらけた本かと思った。意外にシリアス。
タイトルと装丁から、もっとおちゃらけた本かと思った。意外にシリアス。
肥満が病的に蔓延しているアメリカの報告。その原因が、パーム油と高果糖コーンシロップ、ファストフードのバリューセット化ポリシー(!)、教育現場の予算減、過剰な人権保護意識などにあるとする。
教育現場の予算減以外は、すべて今の日本にも当てはまる。現在の政府は、教育にもアメリカ並みに自由競争を取り入れようとしているので、日本も今にアメリカ並みに肥満大国化していくのだろう。なんでもアメリカを追随していると、むちゃくちゃになってしまうぞ。
また、肥満防止や運動推進にかかわるさまざまな公共機関が、ずいぶんいい加減にさまざまな学説を採用してきたことも紹介されている。たとえば「特に運動しなくても体重を減らせる」だの「食事制限などしない方が体によい」だの、行政の都合で、適当な学説が採用され、それに権威付けが行われる過程が示されている。最近の日本のハウツー番組(ダイエット法や健康法を説くテレビ番組)でも、アメリカの学説がさも真実であるかのようにまことしやかに流されているが、あの類の学説も結構怪しいものがあるということがわかる。
翻訳は悪くないが、文章のリズムが悪いせいか読むのに時間がかかった。
![]()
江戸の新発想
『大江戸開府四百年事情』
石川英輔著、講談社
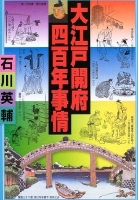 いかにも「江戸開府四百年」キャンペーンにあやかったタイトルで、石川英輔も転んだか……と思わせるが、内容はさにあらず。大江戸事情シリーズの名を汚さぬできになっている。この本を貫いているテーマは、「江戸時代が、一般的に考えられているように暗黒時代であるなら、264年も続くわけがない」という発想である。「だから江戸時代は265年も続いた」というようなフレーズが随所に出てくる。その意味で「江戸開府四百年事情」なのである。
いかにも「江戸開府四百年」キャンペーンにあやかったタイトルで、石川英輔も転んだか……と思わせるが、内容はさにあらず。大江戸事情シリーズの名を汚さぬできになっている。この本を貫いているテーマは、「江戸時代が、一般的に考えられているように暗黒時代であるなら、264年も続くわけがない」という発想である。「だから江戸時代は265年も続いた」というようなフレーズが随所に出てくる。その意味で「江戸開府四百年事情」なのである。
内容は、おおむね今までの大江戸事情シリーズと大きく変わるところはない。大体は焼き直しだ。この本の特色は、他の社会(革命時代のフランス、ソビエト共産主義社会、そして現代)との比較が多いことだろうか。
百姓は重税に苦しみ、米も盆正月しか食べられず、一揆ばかりを起こしていた、民衆は武士に虐げられ、自由な言論も抑圧されていた……というのが、これまでの一般的な江戸史観であろう。
しかし実際には、税率も低く、結構な暮らしを謳歌していたらしい。むしろ武士の方が貧しく、内職が必要な武士が多かったという。
大体、米の生産量は当時の人口を十分まかなえる量があったのに、人口の8割を占める百姓が米を食べずに、生産した米をどうやって消費したというのだろう。ちょっと考えればこんなのは明らかだ。
普通の生活は記録に残りにくい、異常な事態が記録に残りやすい。その点を利用して、異常な事態ばかりをクローズアップしてきたのが、これまでの江戸研究の主流だった。だから、江戸時代の暗部ばかりがクローズアップされるのだ。たしかに米価が高くなり、なかなか米が買えないときもあった(7、8年前の日本でも米が足りなくなったことがあった、タイ米騒動のあれだ)。だからといって、260年間、百姓が米を食べられなかったわけではない。恣意的にそういう印象が与えられていたのだと著者は言うのだ。
歪んだ江戸史観に鉄槌を加える好著。石川英輔の独壇場だ。
![]()
車を捨てよ! 街に出よう
『クルマを捨てて歩く!』
杉田聡、講談社+α文庫
 車は嫌いだ。
車は嫌いだ。
だから免許も持っていないし、移動する場合は、徒歩か自転車、または交通機関を利用する。
第一、車にはデリカシーがない。鈍感だ。横断歩道を歩いていても平気でつっこんできたり(私は追突されたこともある)、雨の日に水をとばして通り過ぎたり(水をとばされるのはたびたびだ)。普通の人間の感性では理解できないよ。街を歩いているときに(車ではなく)そんな人間(しかも巨体の)に出くわしたらどう思いますか、皆さん(ちなみに私はそんな人間に出くわしたことがある)。
そもそも人間は、自動車の速度で走ってはいけないのだ。蠅には蠅の速度がある。象には象の速度がある。人間には人間の速度がある。あの巨体で傍らをすり抜けられるだけでも恐怖を覚える。だが、そんなこと、車に乗っている者には気がつかないだろう。だから鈍感だっちゅうの。
そういうことを常日頃考えている自分にとっては、この本の主張はさして目新しくない。車に依存する生活をやめて歩く生活を送れ、というのがテーマだ。車を捨てると、お金が増え、体力がつき、環境が良くなると言うのだ(「車を捨てると時間が増える」というのはあまり賛同できないが)。こんなことは、自分だっていつも考えている。とは言うものの、こういうことを声高に(本という形で)述べること自体が、非常に有意義なのだとも思う。拍手パチパチものだ。
子供にとって車がどれほど危険なものかを子供の立場になって書いているところもすばらしい。
親は子供に対して「車に気をつけなさい」という。しかし、子供は本来、動きも遅く視野も狭いものなのだから、気をつけるべきは、凶器である車の側だと主張する。ごもっとも。
この著者のエライところは、実際に近所の道路(子供がよく通行し遊び場にしている)を車から解放する運動をやって、成功したことだ。理論家であると同時に実践家でもあるため、きわめて説得力がある。最後に「クルマを捨てる決心の固め方」という章がある。ある意味、ハウツー本なのだ。
何も考えずに車を乗り回している人に是非読んでもらいたい本だ。そして願わくば、車を捨ててもらいたい。あなたの体のためにもネ。
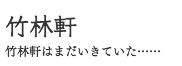
 ホーム
ホーム メール
メール
 前のページへ
前のページへ