「竹林軒出張所」批評選集:ドラマ - 山田太一
|
テレビ放送開始60年記念ということで、テレビと時代をともに歩いた脚本家、山田太一が『100年インタビュー』に登場。そのスクリプトを公開。 |
|
2013年にTBSチャンネル2で放送された『テレビがくれた夢 山田太一 その1』。このインタビューも非常に密度が濃かったので、『100年インタビュー』に続いて書き起こすことにした。 |
|
『テレビがくれた夢 山田太一 その1』に続き、『その2』も放送された。この『その2』では、さまざまな山田作品について山田氏自身がコメントするという構成で、資料的な価値があると思われるので、ひきつづきその内容を掲載しようかと思う。 |
「竹林軒出張所」選集
山田太一のドラマ、マイベスト5
 1. 高原へいらっしゃい(1976年、TBS)
1. 高原へいらっしゃい(1976年、TBS)
2. 日本の面影(1984年、NHK)
3. 二人の世界(1970年、TBS)
4. 沿線地図(1979年、TBS)
5. 岸辺のアルバム(1977年、TBS)
少し前の『ありふれた奇跡』とか、この間の『キルトの家』とかを見てしまうと残念な気持ちがふつふつと湧くが、しかしドラマ作家としての山田太一はやはり偉大である。これだけオリジナル脚本の名作を立て続けに出し続けた人はもう現れないんじゃないかと思う。僕の中では、ドラマの深遠さやストーリーのレベルといった点において、脚本の神様、パディ・チャイエフスキーをもしのぐのである。
実際、山田太一のドラマは、80年代後半以降、見る機会があれば必ず見るようにしていたし、今でもCSやBSで再放送があれば極力録画するというほど見ている。おそらくすべての山田ドラマ(150本くらい?)のうち、半分以上は見ているんじゃないかと思う。そういうわけで、山田太一の代表作は5本と言わず、ベスト10でもベスト15でも選ぶことができるんだが、とりあえずの5本。『午後の旅立ち』や『チロルの挽歌』など、見たいと思っていながらいまだ見ていない代表作もあるので、ベスト6以降は、またいずれ機会があれば、付け加えてまとめたいと思う。 『高原へいらっしゃい』は、高原ホテル建て直しのドラマで、2003年にTBSでリメイクされた。リメイク版は、脚本に山田太一が加わっていなかったこともあって(「山田太一原作」ということになっていた)、どうしようもないものになっていて、リメイクの意味というものを考えさせられる結果になった。だがオリジナルの方は、スリリングな展開といい人間関係の絶妙さといい、まさにテレビ・ドラマ脚本の金字塔と言ってもよい出来映えであった。初めて見たのは中学生くらいのとき(リアルタイムの放送)で、その後再放送を見たくて見たくてしようがなかったが、なかなか見る機会に恵まれなかった。結局数年前にCSのTBSチャンネルで再放送されたものを30年ぶりに全部見ることができたんだが、その感動は子ども時代に見たときと何ら変わっていなかった。昨今も、落ちぶれたレストランの再建ものドラマは頻繁に作られているが、その原点ともいうべき傑作である。また予想外の意外な結末も特筆に値する。出演は田宮二郎、由美かおる、前田吟、北林谷栄、益田喜頓ら。北林谷栄と益田喜頓のオムレツのシーンはあまりに強烈で、はじめに見たときからずっと記憶に残っていたほどである。
『高原へいらっしゃい』は、高原ホテル建て直しのドラマで、2003年にTBSでリメイクされた。リメイク版は、脚本に山田太一が加わっていなかったこともあって(「山田太一原作」ということになっていた)、どうしようもないものになっていて、リメイクの意味というものを考えさせられる結果になった。だがオリジナルの方は、スリリングな展開といい人間関係の絶妙さといい、まさにテレビ・ドラマ脚本の金字塔と言ってもよい出来映えであった。初めて見たのは中学生くらいのとき(リアルタイムの放送)で、その後再放送を見たくて見たくてしようがなかったが、なかなか見る機会に恵まれなかった。結局数年前にCSのTBSチャンネルで再放送されたものを30年ぶりに全部見ることができたんだが、その感動は子ども時代に見たときと何ら変わっていなかった。昨今も、落ちぶれたレストランの再建ものドラマは頻繁に作られているが、その原点ともいうべき傑作である。また予想外の意外な結末も特筆に値する。出演は田宮二郎、由美かおる、前田吟、北林谷栄、益田喜頓ら。北林谷栄と益田喜頓のオムレツのシーンはあまりに強烈で、はじめに見たときからずっと記憶に残っていたほどである。
 『日本の面影』は、ラフカディオ・ハーンをモデルにした全4回のドラマ。出演は『ウエストサイド物語』のジョージ・チャキリス、壇ふみ、津川雅彦など。先日から何度もこのブログで触れている「江戸期の日本の面影」がドラマ全編を通じて登場し、ハーンが目にしたであろう「古き良き日本」が再現されている。もちろんドラマとしても質が高いのは言うまでもない。
『日本の面影』は、ラフカディオ・ハーンをモデルにした全4回のドラマ。出演は『ウエストサイド物語』のジョージ・チャキリス、壇ふみ、津川雅彦など。先日から何度もこのブログで触れている「江戸期の日本の面影」がドラマ全編を通じて登場し、ハーンが目にしたであろう「古き良き日本」が再現されている。もちろんドラマとしても質が高いのは言うまでもない。
『二人の世界』は、初期の山田太一の代表作で、「木下恵介アワー」の1本。その少し前に同じ枠で放送された山田ドラマ『3人家族』の続編みたいな話で、キャストも栗原小巻、竹脇無我、あおい輝彦、三島雅夫と共通する。当初は『3人家族』の恋愛ドラマの部分を抜き出したメロドラマと思っていたんだが、その後急展開してスナック経営話になる。あおい輝彦が歌うテーマ曲もメロウで、子どもの頃から主題歌だけが記憶に残っていた。
 『沿線地図』は、個人的にドラマ全体の雰囲気が非常に好きで、特にフランソワーズ・アルディのテーマ曲(「もう森へなんか行かない」)が何とも言えない。ドラマにもアンニュイな雰囲気が漂っていた。主人公は高校生(真行寺君枝と広岡瞬)だが、思春期独特の閉塞感や焦燥感がよく伝わってくるドラマで、当時同年代だった僕も、共感はしないにしても感ずるところがあったように思う。登場する周囲の大人たち(岸恵子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子)にもそういった閉塞感、焦燥感が伝染していくのも新鮮である。再放送を見たいドラマの筆頭だが、いまだに見れないでいる。
『沿線地図』は、個人的にドラマ全体の雰囲気が非常に好きで、特にフランソワーズ・アルディのテーマ曲(「もう森へなんか行かない」)が何とも言えない。ドラマにもアンニュイな雰囲気が漂っていた。主人公は高校生(真行寺君枝と広岡瞬)だが、思春期独特の閉塞感や焦燥感がよく伝わってくるドラマで、当時同年代だった僕も、共感はしないにしても感ずるところがあったように思う。登場する周囲の大人たち(岸恵子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子)にもそういった閉塞感、焦燥感が伝染していくのも新鮮である。再放送を見たいドラマの筆頭だが、いまだに見れないでいる。
『岸辺のアルバム』も『沿線地図』と同じTBSの金曜ドラマ枠で放送されたもので、台風による増水で流されるマイホームのシーンが有名なドラマである。 家族内にいろいろなゴタゴタが出てきてはこんがらがりながらも、それでも家族はなんとかやっていくという話で、『それぞれの秋』以来、山田太一が何度か取り上げているテーマである。展開に不自然さがなく、また視聴者の目を釘付けにするプロットも見事である。山田太一の名を一挙に高めた作品でもある。出演は、八千草薫、杉浦直樹、竹脇無我、中田喜子、国広富之など。
家族内にいろいろなゴタゴタが出てきてはこんがらがりながらも、それでも家族はなんとかやっていくという話で、『それぞれの秋』以来、山田太一が何度か取り上げているテーマである。展開に不自然さがなく、また視聴者の目を釘付けにするプロットも見事である。山田太一の名を一挙に高めた作品でもある。出演は、八千草薫、杉浦直樹、竹脇無我、中田喜子、国広富之など。
と、こうやって紹介したところで、実際見る機会はあまりないのが現実なのである。どれもDVDは出ていないようで、必然的に再放送に期待するしかないのだが、それもあまり望めないと来ている。僕自身、CSのTBSチャンネルにリクエストしたりしているがいまだにかなわないものが多い。ただ山田太一の作品は脚本が書籍として出版されているものも多く(大和書房など)、こちらも絶版になったものが多いが、図書館には割合置かれているようだ。興味のある方は、そちらから当たられたら良いかも知れない。僕も以前、ブックオフで見つけて、まとめて10冊以上購入したことがある。なお、『日本の面影』については、今でも入手可能である。
続・山田太一のマイベスト+5
 6. 男たちの旅路 第4部「第三話 車輪の一歩」(1979年、NHK)
6. 男たちの旅路 第4部「第三話 車輪の一歩」(1979年、NHK)
7. 今朝の秋(1987年、NHK)
8. シャツの店(1986年、NHK)
9. 夏の一族(1995年、NHK)
10. 深夜にようこそ(1986年、TBS)
番外:ふぞろいの林檎たち(1983年、TBS)
『男たちの旅路 第4部「第三話 車輪の一歩」』は、鶴田浩二主演のドラマで初めて「山田太一」という名前が冠についたドラマだったらしい。このドラマができたいきさつなどは『100年インタビュー』に脚本家本人が登場したときに語られていたので、そちらを参照されたい(『100年インタビュー 脚本家 山田太一(ドキュメンタリー)』)。初めてこのドラマを見たとき、僕は高校生だったが、突きつけられるテーマの重さとそれに対する明快な回答に目からウロコの思いがした。
『今朝の秋』は老いと家族をテーマにした快作。レビューは先日書いたのでそちらをどうぞ(『今朝の秋(ドラマ)』)。 『シャツの店』も鶴田浩二主演のドラマで、鶴田浩二がシャツの仕立て職人になるという珍しい設定の作品。ある夫婦とそれを取り巻く人達の、ときに哀れでときにユーモラスな人間模様が楽しく、セリフが非常に面白かったという記憶がある。
『シャツの店』も鶴田浩二主演のドラマで、鶴田浩二がシャツの仕立て職人になるという珍しい設定の作品。ある夫婦とそれを取り巻く人達の、ときに哀れでときにユーモラスな人間模様が楽しく、セリフが非常に面白かったという記憶がある。
『夏の一族』は、渡哲也が肩たたきにあう研究員の役を演じるという、こちらも異色の設定である。この渡哲也演じる元研究員と、娘を演じる宮沢りえとが対立するシーンで繰り出されるセリフが素晴らしく、それだけでこのドラマの価値があると言える。もちろんストーリーもよくできていて、藤岡琢也や柳沢慎吾との絡みも面白い。テーマはホームドラマ的だが、当時の世相も反映していて、なかなかの快作である。
『深夜にようこそ』は、放送時に1回見ただけで記憶は乏しいが、見たときのインパクトが大きく、なんといってもドラマチックな見せ方に魅せられた。深夜のコンビニに新入りバイトとして入ってきた謎の男を千葉真一が演じるが、どう見てもものすごい遣り手企業人にしか見えず、なぜコンビニのバイトなんかしているのか謎……といった展開である。『春の一族』なんかでも同じように主人公の正体を隠したままドラマを展開させているが、こういったパターンのドラマは見る側を惹きつける上で効果的ではある。山田太一もちょくちょくこういった「謎」を利用したドラマを書いているが、確かに面白い作用を生みだしていて、『深夜にようこそ』はその代表と言っても良いかも知れない。 最後は言わずもがなの代表作『ふぞろいの林檎たち』で、その後第4シリーズまで作られたほど人気が高かった。いかにも連続ドラマという展開の群像劇で、この最初のシリーズと第2シリーズが特によくできていた。第3シリーズはほとんど記憶がなく、第4シリーズは、よくできてはいるがちょっと行きすぎだったような印象がある(第4シリーズについては山田太一自身あまり乗り気ではなかったという話を聞いたことがある)。
最後は言わずもがなの代表作『ふぞろいの林檎たち』で、その後第4シリーズまで作られたほど人気が高かった。いかにも連続ドラマという展開の群像劇で、この最初のシリーズと第2シリーズが特によくできていた。第3シリーズはほとんど記憶がなく、第4シリーズは、よくできてはいるがちょっと行きすぎだったような印象がある(第4シリーズについては山田太一自身あまり乗り気ではなかったという話を聞いたことがある)。
で、今回紹介したドラマは、『深夜にようこそ』以外すべてDVD化されているので、興味のある方はごらんいただきたいと思う。最近、山田ドラマのDVD化が結構進んでいて(山田作品以外のドラマもそうだが)、ファンとしてはうれしい限り。といってももちろんDVDを買ったりすることはなかなかできないのでどうしてもレンタル頼みということになるんだが、有名作以外にもDVD化されているせいか、レンタルに入ってないものも多くなってきた。買うかどうするかちょっとしたジレンマもある。もう少し気軽に見れるようテレビの再放送を増やしていただくとかできないものかと思うんだが。
参考:
竹林軒出張所『100年インタビュー 脚本家 山田太一(ドキュメンタリー)』
竹林軒出張所『テレビがくれた夢 山田太一 その1(ドキュメンタリー)』
竹林軒出張所『テレビがくれた夢 山田太一 その2(ドキュメンタリー)』
竹林軒出張所『その時あの時の今 私記テレビドラマ50年(本)』
2012年2月、2013年4月記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『100年インタビュー 脚本家 山田太一』
(ドキュメンタリー)
100年インタビュー 脚本家 山田太一(2013年・NHK)
NHK-BSプレミアム
山田太一が語るテレビ60年
 テレビ放送開始60年記念ということで、テレビと時代をともに歩いた脚本家、山田太一が『100年インタビュー』に登場。前に見たロナルド・ドーア氏の『100年インタビュー』もなかなか見応えがあった(竹林軒出張所『100年インタビュー ロナルド・ドーア(ドキュメンタリー)』参照)が、この山田太一編も非常に面白かった。
テレビ放送開始60年記念ということで、テレビと時代をともに歩いた脚本家、山田太一が『100年インタビュー』に登場。前に見たロナルド・ドーア氏の『100年インタビュー』もなかなか見応えがあった(竹林軒出張所『100年インタビュー ロナルド・ドーア(ドキュメンタリー)』参照)が、この山田太一編も非常に面白かった。
内容も、テレビ観やテレビドラマの可能性をはじめ、脚本家になったいきさつや、脚本家の名前がドラマのタイトルにつくようになったいきさつ(山田太一が初だったらしい)など非常に多岐に渡り、しかも内容が非常に濃い。あまりに素晴らしいんで書き起こしてここで紹介しようと思ったが、分量が相当なものになったのでやめておく(400字詰め原稿用紙60枚分)。
実際にインタビューの箇所は全部一生懸命入力したんだが、これまでいくつかの『100年インタビュー』のタイトルがDVDや書籍で発売されていることが分かってしまって、ここで全部出してしまうのは問題があるのでは……と思うようになった。それに書籍の形で出るのであれば、何もこんな大変な思いをして入力する必要はなかったんではないかとも思う。結構な労力だったんだ、本当のところ。ま、それでもせっかく入力したんで、著作権を侵害しない程度に以下に一部だけ紹介しておこうと思う。ちょっと読んでいただければわかると思うが、語り口が優しく、それに聞き手の渡邊あゆみが話しやすい雰囲気を作っていて、質問も適切で、インタビューとしては大成功なんではないか……と思いますですねぇ、はい。
なお、この番組で取り上げられ話の中で触れられた山田作品は、『男たちの旅路』、『岸辺のアルバム』、『ふぞろいの林檎たち』、『日本の面影』の4作品。どれも興味深い話が聞けた。『男たちの旅路』の「車輪の一歩」は、僕が山田太一を意識し始めた最初の作品で、その製作のいきさつが聞けたのはとても有意義だった。
★★★★
参考:
竹林軒出張所『光と影を映す(本)』
竹林軒出張所『100年インタビュー ロナルド・ドーア(ドキュメンタリー)』
竹林軒出張所『100年インタビュー 倉本聰(ドキュメンタリー)』
--------------------------
「100年インタビュー 脚本家 山田太一」より
話し手:山田太一、聞き手:渡邊あゆみ
場所:NHK放送博物館

● 脚本家になったいきさつ 渡邊:……テレビって長いこと電気紙芝居って映画の方(かた)に言われてたとか言ってますが……
渡邊:……テレビって長いこと電気紙芝居って映画の方(かた)に言われてたとか言ってますが……
山田:そうそう(笑)、そういう空気、それはもちろん電気紙芝居と言いながら、実はこれはすごく、後でこう広がっていくぞっていう予感はあったもんですから、わざと気がつかないふりをしてたっていうふうなとこもあったり、それからまあ、テレビの方へ行こうかなっていうような人達もきっといたと思いますけれども、私はその中では結構早めにテレビの方へ行っちゃったというか、これはまああの、木下恵介さんという、先生の組に僕はついていたもんですから……
渡邊:松竹の木下恵介組の助監督でいらした……
山田:はい、助監督でしたんで、木下さんがあのー、最後の映画に近い頃ですかねえ、テレビ局の方と代理店の方が木下さんに、なんとかテレビへ来て作ってもらえないかっていうのをすごく……熱心にいらっしゃってたんです。それならあの、松竹との専属契約は切る、で、テレビに一枠持つっていうふうにだんだん決心を固めていかれたんですね。だけどいきなり行ったってテレビわかりませんから……
渡邊:あ、やっぱり全然違うんですか、テレビと映画は……
山田:そりゃもう全然違います。
渡邊:はい、どういう、特に大きな違いというのは……
山田:大体つまり、映画だったらワンシーン1日ぐらいですよね……
渡邊:えっ?
山田:ええ(笑)。
渡邊:そんなに時間かけて撮るんですかっ?
山田:ええ、巨匠の組は特にね。
渡邊:はい。
山田:ですから、そりゃもう、悠々たるものでしたですね。ライティングの時間も長いし……ですから、あのテレビを知らなきゃしようがないっていうんで、木下さんがテレビを少し見てみるっていうかやってみるっていうのかご自分で少しホンを、脚本をお書きになって、で実際に指揮するのはテレビ局のディレクターに任せて、それでそばにいようっていうことになったんですね。しかし木下さんって大巨匠でしたから、お一人でテレビ局へ来られても、テレビ局の人も困るわけですよね。ずっとちょっとそこにいてっていうわけには行かないから。それで誰か一人つけてくれないかって言われて、それで「君来い」って(笑)、木下さんおっしゃったんで、ずっとカバン持ちして局を歩いたんです。
渡邊:修行期間になったわけですね。
山田:そうですね(笑)。ですからそれで僕は割合スムーズにテレビにこう馴染むことができまして、そうすると30分のドラマでしたけれども、1年間続くっていうとそりゃあ木下さん一人でお書きになれるわけがないんで、それで……
渡邊:毎週1本ってことですか?
山田:そうです。で、「君よすか、松竹を?」って……(笑)
渡邊:やめなさいって言われたんですか?
山田:(笑)いやいやいや、やめなさいとは言われない。
渡邊:松竹退社ってことですか?
山田:ええ。まあ要するに、あの僕があまりディレクターに向いていないとお思いになってたのかもわかりません。それで、脚本書く方が向いてると思ってくださったのかもわかりませんが、「それじゃあよします」って言って、それでもう後は「どんどん書け、どんどん書け」って言われて、書いてるうちにライターになっちゃったという。
● テレビの可能性
渡邊:その頃の、テレビの中でのドラマの影響力、一般の人への影響力っていうか、どういう可能性をそこに見られました?
山田:(考え込んで)テレビ界に入っていったときには、活気がものすごくありましたですね、ええ。それでもうみんなで何かやれる何かやれるって、しかも映画とは違うものをやろうっていうような意気込みが非常に局の人達にもあって、それからなんか、すごく映画みたいに時間がかからないで、1本の作品が作れますでしょう。ですから少々実験的だったってあんまりみんな文句言わないで、そういうことで切り開いていった時期だったと思いますですね、テレビの可能性を。で、それからお客様がいろんな他のメディアがある中でテレビをご覧になるんじゃなくて、実にテレビっていうものは珍しいもので面白いもので、そこでつまりドラマがあるっていうことで、毎週ちゃんとみんな忘れないでその時間になったらテレビの前に座るっていうようなね、そういう集中度がありましたですねぇ。ですから反応もこうビビッドにあったりして……視聴率ってのはそんなに言われなかったけども、実感としては、あの頃の方が、テレビの、テレビドラマが社会の中に入り込んでいく力はあったような気がしますですねぇ。
渡邊:その頃のテレビと映画の違いというのは何でした?
山田:長時間、つまり連続(ドラマ)に関して言いますと、長時間時間が使えますでしょ。たとえば10回連続だったら10時間ぐらい。
渡邊:あ、連続ドラマになるから(納得)。映画だったら2時間とか……
山田:まあいくら長くても3時間ぐらいでしょう。テレビドラマの連続ってなると10時間とか20時間とか、長いものはね、そりゃもう全然つまりスピードが違うんですよね。ですから、細かなルールみたいなものもあんまり縛られなくて、で、つまんないことも撮れるっていうんですかねえ……(笑)
渡邊:はい?
山田:あの、玄関入ってきて、こんちはって言ってずっと下駄脱いで上がって茶の間へ来るまで、全部を撮っていく。その一つ一つに芸術的な緊張とかはないんだけれども、そういうところで拾える細かなデテールの面白さ、つまずいちゃったりしても撮り直さないでそのままいくとかね、何かそういう自由感みたいなもの、そして映画だったら省略してしまうようなものをみんな拾えたような気がしますですね。
渡邊:その連続する時間の長さでいろんなことが描ける、ということ……
山田:ええ。つまり事件を追ってどんどんっていうようなものももちろんあの頃もありましたけれども、そういう犯人は誰だ誰だっていうドラマだったらば、他の日常の描写をしたら何を変なところで立ち止まってんだよって怒られちゃうでしょ(笑)。
渡邊:はい。
山田:だけどホームドラマだと、立ち止まっても別に違和感はないわけですよねぇ。
渡邊:自分たちの生活と同じっていうことですからね。
山田:そうそう、そうですねぇ。ですからとりあえずそういう面白さはありましたですねぇ。
渡邊:ああ、書き込めるっていうことですか。
山田:そうですね。つまんないことまで拾えちゃうっていうことね。
渡邊:はい。その、映画ってやっぱり大きなこと扱ったり、非常にインパクト強いものですけれど、テレビってもっと自然に私達の隣にあったような気がするんですが。
山田:そうですね。
渡邊:それはその、ドラマを書く上ではどうなんでしょうかね。
山田:ええ。そこが面白いっていうふうに思いましたですね。たとえば小津安二郎さんの映画なんか、あれは大した事件がない話ですけれども、それでもワンカットにもう何時間もかけて、ほんと2日もかけて「うん」というとこだけ撮るとかいうような緊張と全然違うところで、ドラマは作れていくわけですよね。それの、なんか情けなさもあるけれども(笑)、楽さって言うのかな、なんかその、映画と違う世界、時間が流れているっていう……気楽さもあったと思いますですねぇ。それから、映画と違おう違おうっていうふうにちょっと思っていたところもありますですねぇ。
● 脚本家の名前がドラマのタイトルにつくようになったいきさつ
(脚本家の名前を冠したドラマ、『男たちの旅路』が登場した件について) 山田:あれはあの、脚本家っていうのが本当に名前が出なくて、オリジナルで書いても、まあたとえば、マスコミやなんかもほとんど書いてくれないっていう時期が、まあ70年代の初めあたりですかねぇ、あって……
山田:あれはあの、脚本家っていうのが本当に名前が出なくて、オリジナルで書いても、まあたとえば、マスコミやなんかもほとんど書いてくれないっていう時期が、まあ70年代の初めあたりですかねぇ、あって……
渡邊:普通小説家ですと、小説のタイトルと小説家の名前はセットですね。
山田:そうそう。
渡邊:でもテレビのドラマは、山田太一さんの名前こそその時代出てきましたけど……
山田:出てきてもみんな印象に残ってないっていうみたいになってて、それで倉本聰さんとか向田邦子さんとかと、それから早坂暁さんとか、「なんか悔しいじゃない」というような話はしてたんですね(笑)。そしたらNHKが『土曜ドラマ』というのを今度始めるについては、一人ぐらい脚本家の名前を被したものをやろうと思っていて、お前にその気があれば書かないかって言われて、そりゃもちろん書きますって言いますよね。そしたら、条件は鶴田浩二を主役に書いてくれれば何書いてもいいって言われたんですよね。それで、鶴田さんところへ会いに行って、やっぱり戦争、まだ戦争を忘れない人はたくさんいましたから……
渡邊:70年代まではいましたね。
山田:ええ、ええ。ですから戦争を体験して、同じ世代がいっぱい死んでる人達が、これからのつまり繁栄の日本をね、ただ楽しむっていうんじゃなくて、一人ぐらいは忘れないで、死んだ人達に義理をたてて一人で生きていこうって決心した人、そういう人を描きたいっていうふうに思ってね。そりゃま、鶴田さんが、特攻隊で死んだ人達を忘れられないって……
渡邊:特攻隊の生き残りという人でしたもんね。
山田:ええ、ええ、そういうことを一生懸命熱心にお話しになるんで、あ、じゃあそうしようって。それで私はそれよりも10歳ぐらい若いのかな。だから、もう少し若い人の気持ちもわかるから、中間世代の、若い人と、ま、特攻隊世代との両方を描いてみようと思ったんですね。それで、まあ、ああいう作品ができたんですけども、やっぱりそりゃあ成功しないと、他の脚本家に影響がありますから(笑)、絶対こりゃあ、それこそ視聴率取りたいなと思って(笑)、いつもの僕のやり方とはちょっと違うね、一つのワンテーマを作って、そのテーマにどういうふうに鶴田さんは考えるか、若い人はどう考えるかっていうふうにして、ワンテーマずつ書いていこうと思ったですね。そりゃ非常にテレビ的だったと思いますね。
渡邊:そのテーマが、今でも古くない。バリアフリーの問題だとか、ま「シルバーシート」、お年寄りが電車をジャックしてしまうというね、その発想で、自分の主張というものを訴える。非常にその、社会に切り込んだという印象があるんですが。
山田:そうですね。そういうふうに作ろうと思っておりましたから。
● テレビドラマの訴える力
渡邊:それをあの70年代、もう日本が、戦争を忘れてる世代が多くなってきて、高度成長期を経験し、非常に豊かになっている、そのときにあえてそれを出してくる。というのはどういう……あの……
山田:やっぱり、そういうふうに反応する人間が出てきてもいいんじゃないかとは思いましたですね。みんな、だんだんもう戦後ではないみたいなことを言いだした。ねえ、そうじゃないだろうって気持ちはありましたですね。それと、ひとつずつお年寄りのことは、今とは随分違いますけれども、あの頃は「養老院」って言ってましたですね。
渡邊:そうですね。「養老院」って言葉がありました。
山田:それでお国がお金を出してくださってるから、院長さんの言うことはきかなきゃいけないっていうみたいな。だけど老人たちは、人に言えないけども、おかしいって、俺たちこんな扱い受けるのおかしいと思ってて、それでまあ電車をジャックして、じゃあ要求は何かっていうと俺たちを重んじよとは言えませんよね(笑)。だから要求はありませんとか言って閉じこもってるから。言ったら終わりみたいなプライドがあるわけですよ。ねぇ。だけど無念だ、この扱いは無念だと思ってる人を描いてみたいと思ってて、電車ジャックを……警察にみんな最後は連れて行かれちゃう話ですけども、あのまあ、今でもそうやってジャックしたい老人もいるかもわかりませんですね。
渡邊:それからあのいまだにその、バリアフリー、ユニバーサルデザインっていろいろなことは言われるけれども、けしてそんな十全になっていないというこの、だけど自分たち見てみぬふりをしていたかも知れない、気が付きもしなかった。
山田:そうですね。
渡邊:それをドラマでやられてしまったという感じでしたね。 山田:ええあの……非常に反響も多くて、むしろその、車椅子の人達が社会の邪魔になろうと思って訴え始めるっていうことではジャックと、電車ジャックとちょっと似てるんですけども(笑)、いまだに大学やなんかで「車輪の一歩」っていうのはね、教材に使ってるって方がいますですねぇ。まああれも、随分……3年ぐらい、身障者の方とつきあって、それで、ああこの視点だったら書いてもいいなと思って書いたんですよね。
山田:ええあの……非常に反響も多くて、むしろその、車椅子の人達が社会の邪魔になろうと思って訴え始めるっていうことではジャックと、電車ジャックとちょっと似てるんですけども(笑)、いまだに大学やなんかで「車輪の一歩」っていうのはね、教材に使ってるって方がいますですねぇ。まああれも、随分……3年ぐらい、身障者の方とつきあって、それで、ああこの視点だったら書いてもいいなと思って書いたんですよね。
渡邊:その書いてもいいなというのはどういうことですか?
山田:まあみんななるべくうちにいた方が良いよっていうふうな、外行くと迷惑になるからっていうような……人の迷惑にならないということが一つの美徳として言われていて、それは僕はその通りだと思うけれども、でもギリギリの迷惑っていうものまでかけないようにするっていうことだと、身体の不自由な人達はただうちにいればいいっていうふうになってしまう(笑)っていうことですね。ですから迷惑をかけようっていうふうに、かけてもいいんだよってことを鶴田さんが言うわけですけども、身障者の人達がそういうふうに言うっていうのは、社会的には「なんだこいつら、自分のことを(迷惑を)かけてもいいじゃないかって言う」っていうふうに反感を持つだろう、だからこれを鶴田さんが、みんなは遠慮してんのに「君たちは迷惑をかけてもいいんだ、ギリギリの迷惑はかけてもいいんだ」って言う方が、見てる方(かた)が受け入れやすいでしょうっていうふうに言って、まあその人たちと話しして分かってもらって、それでああいう形にしたんですよ。
渡邊:ああ。でもそういうことを、その、まだ当時茶の間というものが存在したと思うんですけど、家族で見てる中に、こういうテーマをぽーんと投げ込んでくる。メッセージをやっぱり山田さんの場合には、非常に強くこう、あのドラマに関してはそう感じました。
山田:あのドラマはそうですね。もうそういうふうにはっきり、そういうドラマを書こうと思って書きましたですね。
2013年4月記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『テレビがくれた夢 山田太一 その1』
(ドキュメンタリー)
テレビがくれた夢 山田太一 その1(2013年・TBS)
TBSチャンネル2
山田センセイの話を拝聴
 TBSチャンネル2というCSチャンネルがあって、過去のドラマ(もちろんTBS)をまとめて放送するという企画を続けている。そのTBSチャンネル2だが、テレビ番組の制作に深くかかわったスタッフをゲストに迎えて、名作の知られざるエピソードを紹介するというオリジナルのインタビュー番組を30分枠で先月くらいから続けている。その月に放送されるドラマの製作者が多いことを考えると一種の番宣と言えるが、それでも珍しい話が聞けるため、内容は面白く見応えがある。6月と7月は、TBSチャンネル2で山田太一のドラマを大量に放送する関係上、やはり山田太一もこのインタビュー番組に登場してきた。山田太一の話を聞いていると、やはり戦後のテレビ脚本家の第一人者だなと感じる。このインタビューによると、テレビ・ドラマでよく使われているナレーションも山田太一が始めたということらしい。以前紹介した『100年インタビュー 脚本家 山田太一』同様、このインタビューも非常に密度が濃かったので、今回も書き起こすことにした。中には当事者しか知り得ないような、資料的な価値がある情報も多いため、ここで紹介しようと思う。
TBSチャンネル2というCSチャンネルがあって、過去のドラマ(もちろんTBS)をまとめて放送するという企画を続けている。そのTBSチャンネル2だが、テレビ番組の制作に深くかかわったスタッフをゲストに迎えて、名作の知られざるエピソードを紹介するというオリジナルのインタビュー番組を30分枠で先月くらいから続けている。その月に放送されるドラマの製作者が多いことを考えると一種の番宣と言えるが、それでも珍しい話が聞けるため、内容は面白く見応えがある。6月と7月は、TBSチャンネル2で山田太一のドラマを大量に放送する関係上、やはり山田太一もこのインタビュー番組に登場してきた。山田太一の話を聞いていると、やはり戦後のテレビ脚本家の第一人者だなと感じる。このインタビューによると、テレビ・ドラマでよく使われているナレーションも山田太一が始めたということらしい。以前紹介した『100年インタビュー 脚本家 山田太一』同様、このインタビューも非常に密度が濃かったので、今回も書き起こすことにした。中には当事者しか知り得ないような、資料的な価値がある情報も多いため、ここで紹介しようと思う。
内容は確かに深く、充実しているんだが、途中映像を大分端折っているようで、繋がりがあまり良くない箇所がある。そのためこのスクリプトを読んでいて違和感のある箇所がいくつかある。そのあたりは残念。ま、それでも、インタビューの価値はあまり損なわれていないと思う。
案の定と言うか、6月と7月の放送予定作品に関連した話が多く、すでに紹介した『同棲時代』についての話もある。
★★★☆
--------------------------
テレビがくれた夢 山田太一 その1より
話し手:山田太一、聞き手:木村郁美
語り:脚本家、山田太一さん、大学卒業後、映画会社、松竹へ入社。昭和を代表する名監督、木下恵介さんの下で助監督として働き、脚本家への道を歩み始めました。そして、木下恵介アワーやポーラテレビ小説などで数々の名作を世に送り出しました。その後も、独特の手法と着眼点で、『高原へいらっしゃい』、『ふぞろいの林檎たち』、そして『岸辺のアルバム』など、数多くの名作を手がけた、日本を代表する脚本家の一人です。そんな山田太一さんの名作の舞台裏に迫ります。
● 脚本家になったいきさつ 木村:山田さんには伺いたい話がたくさんありますが、まずはこちらに主な作品を挙げてみました。これはほんの一部で、しかもTBSのみですので、他局を合わせますと膨大な数になります。山田さんはご自身の作品がどれくらあるかって把握なさってるんですか?
木村:山田さんには伺いたい話がたくさんありますが、まずはこちらに主な作品を挙げてみました。これはほんの一部で、しかもTBSのみですので、他局を合わせますと膨大な数になります。山田さんはご自身の作品がどれくらあるかって把握なさってるんですか?
山田:いやぁ、してません(笑)。ええ。ある時期、ビデオテープというのはね、どんどん消してしまいましたから、テープが高いということでね。30年間くらいの間のビデオテープは、ドラマに限らず、いろんな分野のものがないわけですよね。テレビ文化っていうものの最初の部分が、フィルムで撮ったものは別ですけども、ビデオで撮ったものは今ないわけですよね。もうこれは取り戻しようがない。その中でまあまあ結構、私は残ってる方かなと思ってね。今になればね、むしろ白黒のテレビの方がなんか珍しくて、時代を感じて面白いっていうふうになったりしますよね。ですから、その、狭い時代の価値観で僕たちはね、やっぱり生きてんだなってことをとても感じますですね。
木村:そうですよねぇ。山田さんは脚本家でもいらっしゃいますが、そもそも脚本家を目指して、この世界に入られたんですか?
山田:テレビ界へね、入ったのは、あの、脚本家として入ってきたという感じですね。その前はね、映画会社にいましたから……
木村:松竹ですね。
山田:ええ、ええ。松竹にいましたし、助監督でしたから。助監督はいわばまあ演出修行をしてるわけですよね。ですから、あの、僕はあの、あんまりその、映画を作りたいとかいう強い思いっていうのではなくて、あの、すごい就職難だったのね。
木村:はい。
山田:それで僕は学校の先生になろうと思って教師の免状はとったんだけれども、コネクションがないと実際には就職できないっていうふうに、まぁ言われたっていうか、そういう状況だったわけね。
木村:はい。
山田:それだから、就職課みたいなところへ、大学のね。聞きにいったら、松竹が撮影所の助監督を募集してるぞっていうんで、それで受けにいったらね……
木村:たまたま次に、松竹の助監督の試験があったからであって、それがなかったらもしかしたら……
山田:なかったら全然違うことをしてたかもわかりませんですね(笑)。
木村:へえーっ。
山田:それで、観客動員数のピークが、私の就職した年なんです。昭和33年(頷く)。ですから映画の監督になろうと思ってる人はいっぱいいたんですよね。
木村:花形の職業だったってことですよね……
山田:花形っていえば……(笑)。
ほんとに不遜なんだけれども、あの、入ってから映画の勉強を、本当に一からさせていただいたっていうかな。木下恵介さんという、ま、当時……今だって巨匠だと思いますけども、その組に私は付くようになって、それで木下さんが、あのー、松竹では思うような映画がもう撮れなくて、つまり巨匠の作るものって金がかかりますから(笑)。だから確実に当たらないとすごい損を抱えちゃうんで、木下さんが申し出る企画っていうのを、松竹がまあ渋ってたわけですね。それで、だんだんつまり辞めようかっていう気分もおありだったと思うんだけれども、あのー、テレビ局がね、代理店の方を通じてだけれども、木下さんに番組を持ってもらえないかっていうオファーを、非常に熱心に来られたのね。私は助監督でいつも割合そばにいましたから、そのオファーの激しさ(笑)、熱心さっていうのもちょっと感動してたところもありました。それで、映画はまだ隆盛でしたから、テレビのあの安っぽい映像なんかのところで仕事をするっていうことは恥ずかしいような感じもあったりしてね。ところが木下さんはやっぱり偉い方だなと思うけど、やってみようっていうふうにお思いになって、木下さんの鞄持ちみたいにして後付いて、「君辞めるか」って、松竹をね、「辞めるか」って言ってくれたときに「辞めます」って言って辞めちゃったんですよね。
木下さんは脚本をたくさん用意しなければ、1年間ずっと連続で書くわけですから。それで『記念樹』っていうのは最初何人かの脚本家に頼んだんですけれども、大半は私と木下さんで書いたんですね。それで1回ずつ物語は違うわけです。俳優さんも違うっていうのを、ずっともう五十何本も続けたんですよね。ですからそれはとても僕は勉強になったし、もうともかく書け書けっておっしゃるわけね。で、ご自分も書くわけですから。それで、書いては持っていくっていうことをしてたら、木下さんが入院なさっちゃったのね。病院へ行って、寝てらっしゃるとこで読むわけですよ。自分で書いた(ものを)……
木村:はい。
山田:それを木下さん、ベッドで目をつぶって聞いてらして、それであそこのあのセリフは要らないとかね、あそこはちょっともう2セリフ増やした方が良いとかっておっしゃるんですよ。それはもうすごい天才的な把握力でね。これで良いっておっしゃるとそれが決定稿ってことになって、廊下にプロデューサーが座って待っててくれてね。
木村:はい。
山田:それで渡すと、そのプロデューサーがすぐ大船撮影所へそれ運んでっていうふうなこともありましたですね。
語り:山田さんが脚本家としてデビューして間もない頃、小説を原作としてテレビドラマ用に脚本化する、いわゆる脚色を担当した作品が、木下恵介アワー『女と刀』でした。
● 『女と刀』について
山田:これ、中村きい子さんっていう鹿児島の作家の小説なんですけど、それを木下さんがやりたいっておっしゃって、木下さんが頭3本くらいお書きになったのかな。それで後二十何本だったかな、僕が書いたんですけどね。それはね、すごく勉強になりました。
木村:勉強になった……
山田:ええ、すごい良い小説でね。中村きい子さんがどこかの新聞に「テレビドラマが終わって」っていう感想の文章をお書きになってね。それでまあ、もちろん褒めてはくださってたんだけど、もうちょっと笑いがあるといいって(笑)書いてあってね。ほんとそうだと、僕はそのとき思いました。うん。自分はやっぱりね、そこまで余裕がなかったっていうかな。ともかく脚色っていうものがこんなに勉強になるんだなっていうことは、とても思いましたですね。
語り:脚本家として初めて連続テレビドラマを一人で手がけたのが、『3人家族』。主人公2人のそれぞれの核家族の姿を描いた作品で、木下恵介アワー歴代最高視聴率を記録しました(最高視聴率は36%、平均視聴率でも30.5%を記録)。
● 『3人家族』について
山田:その頃高視聴率だったんでね、終わったときにね、TBSがちょっとしたパーティを開いてくれたのね。
木村:へぇー。
山田:なんかいろんな代理店の人やなんかが来て、それで「ああ、これで俺は食っていけるかな」と(笑)。ひそかにですけど、誰にも言いませんでしたけど。
● 『パンとあこがれ』について
山田:あの、『パンとあこがれ』っていうのが、ポーラテレビ小説っていうのを始めようと、ま、TBSが企画なさって……
木村:はい。
山田:NHKの朝のドラマと同じ時間帯でやろうっていう、すごいことを考えたんですよ。
木村:NHKの、当時でも朝の小説なんてものすごい視聴率高いですよね。
山田:ええ、すごい視聴率。
木村:その裏にやろうと。
山田:ええ、その裏でやろうっていうんですよ。
木村:わぁ。大役ですね。
山田:それで、その最初のが、最初は楠田芳子さんっていう、木下恵介さんの妹さんの脚本家の方がお書きになったものだったと思います(『三人の母』)。それをやって2番手が僕だったんですね。それで、新宿の中村屋さんの、初代の黒光(こっこう)さんて、黒い光と書くね。奥様を中心に、相馬愛蔵(中村屋創業者)さんってのがご主人なんですけども、それが信州から出て来て新宿でパン屋を始めて、それでだんだんだんだんいろんな問題や出来事があって、インドの独立運動やなんかを助けたりして、匿った人がビハリ・ボース(インド独立運動の志士で日本に亡命。中村屋に匿われる)っていう革命家で、その革命家がカレーライス作ってね(笑)。それであの「カリー」っていう、今でも「カレー」とは言わずに中村屋さん「カリー」って……
木村:「カリー」……はい。あっ、そうなんですか? 知らなかった。
山田:それで、その相馬さんの娘さんが、その人と恋仲になってしまって、それでインド人と結婚をして、その革命家とね。そういう……
木村:そういうドラマなんですか? 山田:いろんなドラマがあるんですよ、面白い(ドラマが)……。ほんとに楽しかった、脚本書いてて。で、俳優さんも宇津宮雅代さんっていう、あの文学座の新人の人がね、やってるうちにどんどんうまくなるんですよ。これはね、やっぱりすごいもんだと思いましたね。女優さんが、こう輝いてくるね。うん。だから視聴率は悪かったんですよ、NHKがもう……
山田:いろんなドラマがあるんですよ、面白い(ドラマが)……。ほんとに楽しかった、脚本書いてて。で、俳優さんも宇津宮雅代さんっていう、あの文学座の新人の人がね、やってるうちにどんどんうまくなるんですよ。これはね、やっぱりすごいもんだと思いましたね。女優さんが、こう輝いてくるね。うん。だから視聴率は悪かったんですよ、NHKがもう……
木村:ああ、その真裏ですもんね。
山田:真裏ですからね。ところが、その真裏だっていうことで、ポーラがスポンサーだったんですけど、そりゃあ(視聴率が)悪くてしようがないっていうふうになってるわけですよ。だけどそれをこう、だんだん認知度を上げていけば良いんだから(と言う)。視聴率のことをおっしゃらないわけですよ。少なくとも僕にはね。それだから、書きたい放題っていうかな(笑)、こっちの気に入るように書けたっていうのかな。それで、「こんなことまで書いても良いですかね」とか言うと「良いんじゃないですか、誰も見てないから」とか(笑)
木村:いやだー(笑)。でも、ある意味相当楽しいですね、それは。
● 『俄(にわか) 浪花遊侠伝』について
木村:あの、『俄 浪花遊侠伝』、これは司馬遼太郎さんの原作を山田さんが脚色なさってドラマ化したんですよね。 山田:ええ、そうです、そうです。それはあの、僕はここんとこはずっとオリジナルで書いていたんですけれども、まあ司馬さんもその、今は神様みたいになっているけど、その頃は特にそんなふうに、良くも悪くも偉くなかったと言うかな(笑)、ええ。で、あの『俄』っていう作品は、大阪の侠客達の話なんですよね。薩長に、ま、いわばやられちゃう側ね、徳川側の人達なんだけれども、(その徳川側が)自分で闘うっていう動力があんまりもう、ずっと平和て来ているからね、それで、まヤクザっていう人達を利用してね、それで闘ったりしたんですよ。その利用されているヤクザたちの話でね、それをとっても僕はいい話だなと思いました。それで、その利用されたヤクザの、まあ長の方が、林隆三さんが若いときで演ってくださってね。ラストになってね、僕はどうもね。その人はね、長生きしちゃうんですよ、ずっと……
山田:ええ、そうです、そうです。それはあの、僕はここんとこはずっとオリジナルで書いていたんですけれども、まあ司馬さんもその、今は神様みたいになっているけど、その頃は特にそんなふうに、良くも悪くも偉くなかったと言うかな(笑)、ええ。で、あの『俄』っていう作品は、大阪の侠客達の話なんですよね。薩長に、ま、いわばやられちゃう側ね、徳川側の人達なんだけれども、(その徳川側が)自分で闘うっていう動力があんまりもう、ずっと平和て来ているからね、それで、まヤクザっていう人達を利用してね、それで闘ったりしたんですよ。その利用されているヤクザたちの話でね、それをとっても僕はいい話だなと思いました。それで、その利用されたヤクザの、まあ長の方が、林隆三さんが若いときで演ってくださってね。ラストになってね、僕はどうもね。その人はね、長生きしちゃうんですよ、ずっと……
木村:司馬遼太郎さんの原作の中だと主役の方は……はい。
山田:事実ですからそれはそれでしようがないんですけどね。僕はね、これ最後にこうパッとすごいでんぐり返る話がね、そういうようなものが書きたくて、それで司馬さんにね、僕考えた上で……ずっと利用されたまんまではなくて、最後に大阪で戦争があるときに、侠客達が全部親分の周りにいて、明治維新側に裏切っちゃうぞと……
木村:大どんでん返しということですか?
山田:そうそう(笑)。それで裏切っちゃうという話を書きたくなったのね(笑)。そりゃひどいことなんだけど、司馬さんもまだそのね、そういう学者みたいなふうではなかった。いくらかまだ少し大衆小説を書いているというお思いがあったのか、失礼かも分からないけど、ま、失礼ではないと思いますけどね、そういうわくわくするような話っていうのも良いと思うって言ってましたけども。
木村:それはあの、ラストシーンを変えても良いですかってお伺いしたんですか?
山田:ええ、ええ、そうです。そしたら、良いよっておっしゃったんで……
木村:あ、そうですか。
山田:ええ。ですから、その頃は司馬さんももちろん事実を基にしてるっていったって、『坂の上の雲』みたいな、ああいうふうに事実じゃないわけですよ。それをま、ネタにして、面白おかしい侠客の話を書いてるわけですから、そんなに抵抗はなかったんじゃないかなっていうふうに思いますけども。
語り:そして上村一夫さんの人気劇画を脚色した『同棲時代』。1970年代の若者の貧しくも爽やかな同棲生活を、沢田研二、梶芽衣子が熱演しました。
● 『同棲時代』について
山田:この辺で僕は脚色が嫌になっちゃったっていうか、止めようと思ったのね。
木村:それはなぜですか?
山田:えっ、だって人の作品でしょう。つまんないじゃないですか。だって自分が作家になろうと思って、こう歩き始めたのに人の作品をこう技術的にテレビ向きに書くっていうこと、それは決して簡単ではないわけですよ、人の作品ですから。その人に対する敬意がなきゃいけないし。
木村:あの、沢田研二さんが主役ですよね。
山田:ええ、沢田研二さんがね。僕は大体キャスティングの3人か4人決まってからじゃないと書き出さないんですよ、ええ。俳優さんによってこう、インスパイアされるっていうのかな、この俳優さんだったらどういう物語になっていくだろうっていうね、大雑把な物語は考えているけど……
木村:はい。
山田:でもある俳優さんが掴まるか掴まらないかで、やっぱり話が変わってきますよね。オリジナルだとね。
木村:へぇ—。
山田:原作だったらそうはいかないでしょ。
木村:まぁ、そうですよね。
山田:当時、新聞のね、今でもちょっとそういうとこあるけど、脚本の名前なんか出ないんですよ(笑)。
木村:うーん。
山田:ですから『浪花遊侠伝』なんか連続ですけれども、そりゃもちろん「司馬遼太郎原作」ってなっちゃいますよね。それでそれは、倉本聰さんとか早坂暁さんとか向田邦子さんとかも無念だと思っていたわけね(笑)。
木村:忸怩たる思いがありますよね。
山田:悔しい……
木村:はい。
山田:それで新聞の人達と会ったりすると「名前出してよ」とか言ってたわけね(笑)。このままずっと便利に脚色で使われてると、そういうライターになっちゃうっていうふうに思ってね、これは少し売れなくてもいいやっていうかな、「オリジナルで行こう」って思ったわけね。それでそれが、倉本さんなんかも向田さんなんかも思ってた時期なんですね。そういう時期だったっていう気がするな。僕一人でそんなふうに切り開いたわけじゃなくてね。
語り:その後、山田さんのオリジナリティを確立していくきっかけとなった作品が『それぞれの秋』。効果的にナレーションを加え、新しい辛口ホームドラマのスタイルを築き上げました。
● 『それぞれの秋』について
山田:木下恵介アワーとかいうことは気にしないで書きたいものを書いてみろって言われたのね。それで書こうと思ったのね。で、家族の話っていうのが割合アットホームな家族のシリーズものが当たってた時期だったんですけども、僕はそういう家族は書きたくないって思ってて、しかしその、なんとも荒れ狂ったような家の話とかってね、そういうのも書きたくないのね。それで、いろいろ考えて、まこれ「ドラキュラドラマ」ってその頃、僕がちょっとしゃべったもんだからそう言われたんですけれども、あの、首筋に血を吸われた跡がこう……
木村:見てます。
山田:それで血を吸われた人間はもう、吸血鬼になってるわけですよ。
木村:はい。
山田:だけど普通は、普通の恰好して普通にしゃべっているわけですね。で、首筋見るとアッて(思う)……こんな太い薪みたいなのでこうやってガンと胸をやって殺しちゃわなければいけないっていうね。僕が、家族がみんなドラキュラみたいになる話を書けないかなって思ったのね。
木村:それはドラキュラの映画を見て思い付いたんですか?
山田:そうそう(笑)。
木村:へぇー。
山田:良い家族だとみんなで思ってるんだけど、実は隠し事をみんな持ってるわけですよ。そりゃまあ人って何かの隠し事を持ってるもんだってチェーホフが言ったけども、ほんとにま、そうですけどね。それで中心になるのは、小倉一郎さんが若い頃に演ってくださったんだけど、男っぽくない子ね。
木村:すごいはまってらっしゃいましたよね、私このドラマ見ましたけども。
 山田:あ、そうですか。フニャフニャした男って(笑)。
山田:あ、そうですか。フニャフニャした男って(笑)。
木村:(笑)。
山田:友達にそそのかされて、痴漢を1回やってみろって言われて、それでうっかり高校生のお尻触っちゃうと、腕捕まれてこうやってやられる(腕を上げる)と、それが高校の女性の番長なのね。
木村:桃井かおりさんですね。
山田:そりゃあ桃井かおりで怖いよね(笑)。それで、小倉一郎を好きになっちゃうわけですよ。そうすると迷惑なわけだけど(笑)、痴漢やったって言うぞって言われるとちょっとどうしようもなくて。それでグループに行くと、妹がそこにいるわけですよ。つまりみんな、えーっ、何なんだ、俺は痴漢で、妹はそういう……
木村:スケバングループの一員になってて……
山田:……だってビックリしちゃう。
木村:妹のこの首筋に歯の跡があった……
山田:歯の跡があったという……
木村:そこで見ちゃうっていうことですよね。
山田:そうです、そうです。それで、あの、お父さんが脳腫瘍になって。それはあの脳腫瘍のある話を『暮らしの手帖』っていう雑誌で、どなたかが体験エッセイを書いてらっしゃって、脳腫瘍に主人がなって、もうあらぬことを言いだしてしまって、それが家族に対する不満だったり内面の、ちょっと人には聞かせられないような気持ちとかをしゃべっちゃったり。そういうのは全部、先生が、お医者さんが、これはあの、全然本心とは関係がありませんって言うわけですよね(笑)。これは病気が言わせてるんだから、それを真に受けて苦しんだりしちゃいけませんって言うんだけど、ものすごく内面の告白なんかにリアリティがあるもんだから、これはやっぱり……
木村:家族としてはつらいですよ……
山田:やっぱりこれっていうふうに、そういう装置を使って、普通の人がだんだんだんだんみんな内面にはなんか暗闇を持ってるっていうふうに書いていた話を、それこそ『女と刀』のとき言われたんじゃないけど、笑いを入れるってことでおかしい話にして、書こうと思ったのね。
木村:温かい人情味あふれるホンワカ・ホームドラマが流行っている時代で、あえてそういう辛口ホームドラマって言っていいんでしょうか、そういうものに挑戦しようと思われたのは……どういうメッセージがあったんですか?
山田:それは、もうものすごくアットホームなね、お祖父さんがいてお祖母さんがいて、両親がいて、それで家族兄弟が大勢いてっていう、そういうものは実際にはもうどんどん減ってたわけですよ。核家族っていってね。両親と子どもだけっていう、それがいわば標準家庭みたいに言われだしていた頃に、そういう大家族の話を書くっていうことは、いわば今失われていくものだから書く、そして見たいと思うという要素も僕は絶対あると思ったけども、そこへ遅れて参入したってかないっこないわね。あの、向田さんなんかがいるんだから(笑)。それだから僕がでていく意味って考えると、やっぱり核家族。で核家族がうまく行ってますっていうんじゃなくて、核家族の暗闇を描くっていうことはいずれそうなるだろうと思った、ドラマが。そういつまでもいつまでも、お祖父さんの知恵で解決するとか、お母さんの情で解決するとかいう話は、だんだんみんな、白々しくなって見なくなるだろうと思ったのね。それだから、割合確信犯的にドラキュラドラマを(笑)……
● ドラマの「語り」について
木村:その後に追随してくるドラマってみんな辛口ホームドラマで、その後、随分増えますもんね。その増えるといえば、『同棲時代』もそうなんですが、いわゆるモノローグっていう、独り語りのナレーションをすごく山田さん、多用なさいますよね。
山田:要するに映画界は、ナレーション、語りで見せるっていうことは、非常に邪道だと言われてたんですよ。その存在、動き……
木村:映像で物語らなきゃいけないと。
 山田:そうです。だから回想だって、回想入れると「えぇっ」て言うくらい、映画はそういうの嫌いだったわけね。「私はこう思った」なんてそんなの言うなって、映しゃ分かるんだっていうのが映画の流儀、それは僕はそれで非常に正しいと思う。今でも正しいと思うけれども、テレビへ来たら集中度が悪いわけ、見てる人のね。電話がかかってきたり、トイレ行ったり、新聞開いたりで見てるわけですよ。それに集中して見てないとわからないようなドラマを書いたってね、通じないだろうと思ったのね。それで、ナレーションを入れようかと思ったのは『3人家族』なんだけども、それまでのアメリカのテレビが『逃亡者』っていうかなり有名な、その後ハリウッド映画にもなりましたけども、連続ドラマがすごく評判が良くて、それを日本語に吹き替えていたナレーションを矢島正明さんっていうね、日本のナレーターの方がやってくださっていた。そりゃもう有名な方ですけども、それ見てて「矢島さんのナレーション使いたいな」って思ったわけね。
山田:そうです。だから回想だって、回想入れると「えぇっ」て言うくらい、映画はそういうの嫌いだったわけね。「私はこう思った」なんてそんなの言うなって、映しゃ分かるんだっていうのが映画の流儀、それは僕はそれで非常に正しいと思う。今でも正しいと思うけれども、テレビへ来たら集中度が悪いわけ、見てる人のね。電話がかかってきたり、トイレ行ったり、新聞開いたりで見てるわけですよ。それに集中して見てないとわからないようなドラマを書いたってね、通じないだろうと思ったのね。それで、ナレーションを入れようかと思ったのは『3人家族』なんだけども、それまでのアメリカのテレビが『逃亡者』っていうかなり有名な、その後ハリウッド映画にもなりましたけども、連続ドラマがすごく評判が良くて、それを日本語に吹き替えていたナレーションを矢島正明さんっていうね、日本のナレーターの方がやってくださっていた。そりゃもう有名な方ですけども、それ見てて「矢島さんのナレーション使いたいな」って思ったわけね。
木村:はい。
山田:それでここで使ったんですよ。で、そうやって『それぞれの秋』のときは、今度は小倉一郎さんの口調、小倉一郎さんのしゃべりで入れる。それはつまり単に説明ではなくて、それも描写の一種ですよね。僕はそれは良いと思ったの、そういう描写になればね。効果音としてここで雀の声を入れるとかウグイスを入れるとかっていうのと同じように、もう作品の中に入っているものだ、テレビと映画は違うんだからお客様に届かなきゃしようがないんだから、っていうんで入れたのね。
ま、あの倉本聰さんがね、ああこういうのやっても良いんだって思ったっておっしゃってくださったのは、倉本さんも映画育ちでしょ。だからナレーションやモノローグなんて、「バカヤロー、入れるんじゃねぇ」って言われて書いてたわけじゃないですか。おずおずやっても良いんだっていうふうになってって、きっと『北の国から』は、あの坊やのね……
木村:山田太一さんが突破口を開いてくださったわけですね。
山田:(笑)いえいえいえ、そういう意味で言ったんじゃない。倉本さん怒るかもわかんない(笑)。
2013年6月記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『テレビがくれた夢 山田太一 その2』
(ドキュメンタリー)
テレビがくれた夢 山田太一 その2(2013年・TBS)
TBSチャンネル2
脚本家本人による作品解説
 前に紹介したTBSチャンネルの対談番組、『テレビがくれた夢 山田太一 その1』に続き、『その2』も放送された。この『テレビがくれた夢』シリーズは、TBSで仕事をしたテレビ関係者がインタビューを受けて、さまざまなTBS製作ドラマについてエピソードなどを語るという企画だが、山田太一はやはりテレビ界の重鎮ということで2回に分割して放送された。『その1』が30分、『その2』が30分で都合1時間の対談ということになる。この『テレビがくれた夢』シリーズの放送に伴い、TBSチャンネルで、過去のいろいろなドラマが放送されていて、そのラインアップは非常に華やかである。山田太一のドラマもご多分に漏れず、TBSで話題になった山田ドラマは今回全部放送されているんではないかというほどの充実ぶりで、30年来待っていた『沿線地図』まで放送される(9月21日)。うれしい♡。
前に紹介したTBSチャンネルの対談番組、『テレビがくれた夢 山田太一 その1』に続き、『その2』も放送された。この『テレビがくれた夢』シリーズは、TBSで仕事をしたテレビ関係者がインタビューを受けて、さまざまなTBS製作ドラマについてエピソードなどを語るという企画だが、山田太一はやはりテレビ界の重鎮ということで2回に分割して放送された。『その1』が30分、『その2』が30分で都合1時間の対談ということになる。この『テレビがくれた夢』シリーズの放送に伴い、TBSチャンネルで、過去のいろいろなドラマが放送されていて、そのラインアップは非常に華やかである。山田太一のドラマもご多分に漏れず、TBSで話題になった山田ドラマは今回全部放送されているんではないかというほどの充実ぶりで、30年来待っていた『沿線地図』まで放送される(9月21日)。うれしい♡。
 そういうこともあって、この『その2』では、今回放送されるさまざまな山田作品について、山田氏自身がコメントするという構成で、『その1』ほどの面白味はないが、それでも資料的な価値があると思われるので、『その1』にひきつづきその内容を再び掲載しようかと思う。途中聞き取れない箇所があったため、その辺は適当に省略している。また面白味のない箇所も適宜省略している。
そういうこともあって、この『その2』では、今回放送されるさまざまな山田作品について、山田氏自身がコメントするという構成で、『その1』ほどの面白味はないが、それでも資料的な価値があると思われるので、『その1』にひきつづきその内容を再び掲載しようかと思う。途中聞き取れない箇所があったため、その辺は適当に省略している。また面白味のない箇所も適宜省略している。
内容的には、なんといっても音楽に関する話が興味深かった(70〜80年代の山田作品は音楽がとにかく素晴らしい)。それにしても『高原へいらっしゃい』が『七人の侍』だったとはね……。
★★★☆
--------------------------
テレビがくれた夢 山田太一 その2より
話し手:山田太一、聞き手:木村郁美
語り:まずは、ラジオの深夜放送の世界を描いた『真夜中のあいさつ』。せんだみつお演じるリスナーからの手紙をきっかけに、彼が思いを寄せる女性を番組の中で探し出し、恋を実らせようと周囲の人々が応援するというストーリー。
 ● 『真夜中のあいさつ』(1974年)について
● 『真夜中のあいさつ』(1974年)について
山田:ずっと経って、あの『電車男』っていうのがあって……あれはあの、ラジオじゃないですよねぇ。だけど構造としては……(笑)。
木村:そうですよね、私も思いました、見てて。あ、なるほど、ネットかラジオかの違いですよね。だんだんみんながこう……
山田:知らない人同士が集まってくるっていう話をねぇ。メディアのツールが変わってくるからね。あの、で、両方似たようなことを考えてんだなと思いましたけどね。
木村:当時の時代背景を、すごくこのドラマを通じて知ることができたのが、本当に当時の若者とかいろんな方々、深夜のラジオを熱心にああやって聴いてたんだなっていう……
山田:ええ、ええ、そうですね。それ僕、面白いと思ってね、で、書いてみたんですよ。
語り:続いての作品は『高原へいらっしゃい』。田宮二郎演じるマネージャーが、経営難に陥ったホテルを再建するべく、自らスタッフを集め、奮闘する姿を描いた作品です。実はこの作品も、意外なところから発想されたそうです。
● 『高原へいらっしゃい』(1976年)について
山田:このときはね、『七人の侍』、あれはあの手練れの侍をこう雇う話じゃないですか。だんだんみんな、ね。
木村:そうですね。
山田:あれをじゃやってみようかなと思ってね、それで信州の高原の、廃屋近くなってきたホテルを再建することを頼まれて、「やろう」と思って、それで街中へ行ってウェイトレスを見てて、このウェイトレスに声かけてみようとか、中年の男に声かけるとかいろんな風にして……
木村:それが七人の侍なわけですね。 山田:そうそう、七人の侍みたいに集めて……。それでみんなは誰に声かけられたんだかわかんないまんま、あそこのホテルへ、廃屋みたいなホテルに来て、ロビーでみんなで座ってると、こう、らせん階段の上からね、田宮二郎が「皆さん、よく来てくれた」っていう風に、そういうかっこつけてもおかしくないでしょ、ホテルの支配人だからね。
山田:そうそう、七人の侍みたいに集めて……。それでみんなは誰に声かけられたんだかわかんないまんま、あそこのホテルへ、廃屋みたいなホテルに来て、ロビーでみんなで座ってると、こう、らせん階段の上からね、田宮二郎が「皆さん、よく来てくれた」っていう風に、そういうかっこつけてもおかしくないでしょ、ホテルの支配人だからね。
木村:どういうところで、この脚本、こういうドラマを描こうっていうアイデアって生まれてくるんですか?
山田:いや、それは(笑)……こっちがつまり、もう食べていくっていうことが基本にあるからね。やっぱり切実ですよ、良いもの作らなきゃいけないと思ってるからね。だからしょっちゅう針は動いてますよね。で、たとえば『高原へいらっしゃい』は『七人の侍』のパクリだとは言われないでしょ(笑)。そういう風に全然違えばいいわけですよね。
木村:でも、ちょっとしたヒントっていうのはその日常生活の中に常にこうアンテナを張り巡らせて……
山田:そうです、そうです。
木村:手に入れてるんですか。
山田:ええ、そうですね。で、何もかも新しくやるっていうことはできませんですよ、人間ってね。前世代から積み上げてきたものを踏み台にして、次の物語を書くわけだけども、テレビはあの、前世代っていうものがなかったじゃないですか。それだから、やっぱり映画を参考にせざるを得ないですよね。それで、書いていくうちに、映画とテレビは違うっていうことにだんだん気が付いてきたわけね。それで、ナレーション使ったり、あの手この手をね、「つづく」っていう風に書くだけだって違いますよね。映画は「つづく」っていうのはあまりないですよね(笑)。
木村:「完」ですもんね。
セリフというか言葉使いとかも、すごいホントに今の時代とも違う……特に『岸辺のアルバム』の八千草さんの口調とか、私すごい真似したくなるぐらい、「〜かしら」とかすごい素敵だと思うんですけど、そういう会話の、言葉の使い方っていうのも、日常こういろんな人の会話を聞いて書いたりするんですか?
山田:ええ、そうですね、まあ、あの俳優さんに合う言い回しっていうのは考えますけれども。
その辺の食堂みたいなとこだと相席っていうのが当たり前だったのね。それだから、込んだときに行くと相席になるでしょ。で、それで一人ずつの相席だと何も面白くもなんともないけど、向こうがあの、2人くらいで、その、問題抱えてるおばさんとそれに何かこうね、忠告をするおばさんが2人で座ってしゃべり出すとね、僕がいることなんか忘れちゃうのね。「もしもし僕聴いてますよ」って言いたくなるようなことだってしゃべってんのね。それ、おかしかったけどね。でそういうときにすごく……まそう滅多にないけど、「ウワッ、使いたい」っていうセリフを言ったりする人がいるわけですよ。それを使うために考えようとか思って、で書き終わってみると、そのセリフはないのね。まず、ないことが多いな。
木村:へーっ。
山田:つまりね、自分を通すと、やっぱり自分に合わないセリフはね、面白いけどカットしちゃうわけね。しかしその、テンション、凡庸じゃないセリフ……っていうのはやっぱり、それに負けないようにこっちが書こうと思ったら……
木村:たぶん、山田太一さんの中で変換して、山田さんの温度で言葉に変えていくわけですよね……
山田:そうそう、負けないくらいのところで維持しようとするっていうふうに……「そうなの」「うん」っていうふうに、こうなめらかに流れないように(笑)書くとかね。なんかそういう、ある教訓みたいにしてそういうセリフを手にするって言うかな。あんまり実際には使ってないんだけどね、だけど刺激になる。
木村:(フィルモグラフィのフリップを指して)この『岸辺のアルバム』は、山田太一さんご自身がお書きになった小説をご自身が脚色なさったドラマですね。
山田:そうです。
木村:このまたタイトルからすると、なんてホンワカしたと思いきや……衝撃的な内容ですよね。
語り:倦怠期を迎えた夫婦の危機と、大人になっていく過程で悩みを抱える子どもたち。そんな家族が崩壊していく姿を描いた『岸辺のアルバム』。多摩川の洪水で家が流され、家族が大切なものを取り戻すというストーリー。辛口ホームドラマの名作として、ドラマ史に残る作品です。
● 『岸辺のアルバム』(1977年)について
山田:もうずっといっぱい書いてるわけですよね、他の局やなんかで。そうすると、なんかそうじゃない世界のものを書きたくなるのね。テレビでは企画は通らないだろうけれども、でもやりたいなっていう。そういうときに新聞社の人が、「あなた新聞小説書けそうだから書かないか」って言ってきてくださったのね。それで書いたんですよ。だからあの、通りそうな企画を出すわけじゃない、何書いたって良いってんだから。もう、家族にいろいろ暗い部分があって、しかもそれ全部流されてしまう、最後。その上で、ある、こう、この第一歩が始まるっていう話をね、書いてみようと思って書いたんですね。で、途中まで連載が続いてるときに、もうTBSが「テレビにしたい」っておっしゃってくださって、これはうれしかったですよ、とっても。こんな暗い話、最後にみんななくなっちゃうのなんか、テレビで企画だけ、書類だけを出したらね、とんでもないって言われちゃうと思うのね。だけど小説に書いたっていうことで、ある種のオーソライズをされたっていうのかな。
俳優さんもすごかったけども、こう皆さんでこうカーッとやろうっていうのかな……
木村:伝わってきました、見てて。
山田:それはね、うれしかったですね。
木村:これ、でも、すごい印象的だったのは、あの「ウィル・ユー・ダンス」。
山田:あ、そうそう。それは堀川とんこうさんっていうプロデューサーがね、なんか前にジャニス・イアンでドラマ……一つ使ったんだそうです(注:『グッドバイ・ママ』のこと)。そしたら、ジャニス・イアンの方でその許可を出すときに、もう1回、ジャニス・イアンを使ってくれればっていうようなことがあって、どっかでジャニス・イアン使おうと思ってらっしゃったっていう……
木村:使わなきゃいけなかったわけですね(笑)。
山田:そうそう(笑)、そういうようなことをおっしゃってたけど。でもその「ウィル・ユー・ダンス」っていう曲、あの歌詞、もう陰々滅々とした歌詞ですよ。その辺で死んでる人見ても知らん顔してようとかね、親が子どもにね、我が家がすばらしい家庭だって騙しておこうとかね(笑)。そういうすごい歌詞で。それで、そういう歌詞だって感じさせない、甘い……
木村:メロディが全然違います。
山田:すごいじゃないですか。あんな、つまり根性のある歌。で、しかも甘い曲、っていうのをよくまあ見つけてくれたなって思う、僕は。それとね、それから連続のタイトルの最初に1回目から洪水の映像を見せちゃってるってことね。あれもね、僕はプロデューサーの力だって、とても思いましたね。
木村:先にエンディングを見せちゃうというのは、かなり新しい手法ですよね。
山田:(笑)そうですよ。ええ、よくあんなことやったなと思いますねぇ。感謝してます、歌も含めてね。で、あのねぇ、良い作品ができるときってねぇ、不思議なくらいスタッフやなんかみんな、こう良い人達で集まるっていうと語弊があるかもわかんないけど、みんなこう割合グッとやろうっていうタイミングのときってのがあるのね。
 語り:山田さん原作の小説を自ら脚本化した『沿線地図』。何不自由なく生活していた優等生の若者が、高校を中退し同棲生活を始めた。さまざまな問題を抱える家族の姿を通して、幸せとは何かを問いかける作品です。
語り:山田さん原作の小説を自ら脚本化した『沿線地図』。何不自由なく生活していた優等生の若者が、高校を中退し同棲生活を始めた。さまざまな問題を抱える家族の姿を通して、幸せとは何かを問いかける作品です。
● 『沿線地図』(1979年)について
木村:あの、この『沿線地図』も主題歌、すごい良かったですね(フランソワーズ・アルディの「もう森へなんか行かない」)。
山田:ええ、これも片島謙二さんっていうね、もうホントに『岸辺』のときからそうなんだけども、プロデューサーの助手さんだったかな、その頃は。もう音楽がすごく好きな人でね、僕は『同棲時代』であの……
木村:吉田拓郎さん。
山田:そうそう、あれもね、片島謙二さんから教育されたのね(笑)。
木村:ああそうですか。
山田:「とっても良いからね、拓郎で」っとか『同棲時代』で言って。それで僕はもう、僕も好きになってたから、あの、使うっていう風になって。それで、サザンの『ふぞろい』もそうなんだけれども……
木村:『ふぞろいの林檎たち』、はい。
山田:片島さんが担当して、音楽の方のプロデューサーになってくれてると、ホントに僕を傷つけないでね、3曲ぐらいいろんなアーティストのアルバムを送ってきて、それでこの3人の中でどれを選びますかとかいう風に訊いてくれるわけ。
木村:あ、最後の選択権は山田さんにあるんですね。
山田:って、あるかのごとくにね。ところが聞くと、その、目玉のものが一番良いようになってるわけです(笑)。
木村:(笑)それを選ばざるを得ないような状況があるわけですね(笑)。
山田:(笑)だけどね、それの、とてもそういうところがナイーブでね、うれしかったですね。それだからサザンもそうでしたけど、『沿線地図』もフランソワーズ・アルディの曲でしたけどね。
笠智衆さんの、僕は笠智衆さん好きなんで、笠智衆さんに出ていただいたんだけど、それが児玉清さんのお父さんの役で、それで、妊娠しちゃうんですよ、その高校生の女の子が。「絶対、お前生め」っておじいちゃんは言ってくれるだろう……と思って行くんです。そうすると「つまらんよ、生むことはない」って言われちゃうのね。それで「えっ」て、「ヒューマニズムじゃないんだ」とか(笑)ショック受けるわけね。それで少し経つと、おじいちゃん首吊って死んじゃうんですよ。つまりもう、他のお父さんたち、児玉清さん世代は、もうおじいちゃんを別居させて放ってあるわけですよ。それで「つまらん」ってんで死んじゃうんですよ。それで児玉清さんがものすごくショック受けてね、首つりの紐をこうやってほどいてね、座り込むシーンがあるんですけどね。
● 『想い出づくり。』(1981年)と『ふぞろいの林檎たち』(1983年)について
語り:続いて結婚を意識した24歳の3人の女性が結婚までに青春の想い出を作ろうとするドラマ、『想い出づくり。』。複数の主人公、それぞれのストーリーを描く、いわゆる群像劇というスタイルを打ち出した画期的な作品として、ドラマ史に残る名作です。
 山田:24のときはクリスマスケーキと同じとか言う、あの頃。今考えるとよくそんなこと言ったなと思うけど、翌日25日になるとクリスマスケーキは売れなくなっちゃう……。婚期っていうのは24までで、25になったら遅いっていう……
山田:24のときはクリスマスケーキと同じとか言う、あの頃。今考えるとよくそんなこと言ったなと思うけど、翌日25日になるとクリスマスケーキは売れなくなっちゃう……。婚期っていうのは24までで、25になったら遅いっていう……
木村:あ、そういう時代だったんですか。
山田:そういう時代だったんですよ。で、僕は娘が2人いたもんだから、こんな常識はとんでもないと思ったわけね。それ壊そうって思ったのね。で、それと同時に、あの、どうもつまり主役2人だけ光が当たって後はみんな奉仕する役柄っていう……脇役っていうのが、僕はこれもう壊す時代だって。あのー、つまり、えー、みんなで自分が偉いって思ってる時代じゃないですか、民主主義だったから。
木村:はい。
山田:そのときにドラマだけがね、なんかこう2人の男女のきれいなのがいて、後は奉仕するっていうのは……恋敵とかだってね、恋敵という役にもう固定されてしまうわけでしょ。そんなドラマはね、早晩壊れちゃうだろうって思ったのね。それであの、3人の24の女の子を選んで、それでどの人に訊いても本当のこのドラマの主役はあなただって言うとね、その3人とも本当はそうだなって密かに思うっていうドラマ書こうと思ったの。
木村:これ、いわゆる群像劇のスタイルを初めて打ち出したドラマでしたよね。
山田:そうですね。
木村:これはあの、複数主人公がいるという意味では、(フリップを指して)この『ふぞろいの林檎たち』もそうですよね。
山田:そうそう、それで『ふぞろい』のときに人数増やそうと思ったわけね(笑)。
木村:(笑)3人からもっと増やして。
山田:中井さん、柳沢慎吾さん、みんな自分が主役だと思ってくれないかなと思って書いたわけね。それとその、政治の季節がこう、だんだんだんだん終わってきたときでね。で、こういう、なんていうか勉強あまりできない男3人が、配達を頼まれて配達に行くと、みんなヘルメットかぶってる人達が潜んでて、そこで集会をやるっていう。それで「君たちも大学生なのに、日本のことを考えなくて良いのか、世界のことを考えなくて良いのか」とかなじられちゃうわけ。それでも配達して3人でしょんぼり帰ってくるんだけど、僕はそっちが素敵だと思っちゃうわけね。その、政治のことなんか言ってる奴の、理念のインチキさっていうのは、もうずっと大学の頃から僕は感じてたから。
勉強ができない人たちのチャーミングさ、魅力、東大の前の酒屋なんだけど、東大へは配達では何度も行ってるけど、自分は入れないっていう(笑)。
木村:入れない(笑)。
山田:そういう話を書いたんです。
語り:辛口ホームドラマ、青春群像劇などのスタイルを確立した山田さんは、その後も斬新な発想で時代を捉えた作品を生み出していきます。
● 『輝きたいの』(1984年)と『深夜にようこそ』(1986年)について
木村:この『輝きたいの』は女子プロレスラーの方が主人公の。
山田:そうです。
木村:女子プロレスをご覧になって、好きだったとか?
山田:いえいえ、そんなに好きじゃなかったですけども。
木村:(笑)
山田:なんかあの、アナウンスが独特で、うわーってとこに女の子が出て行くっていうのが、なんか意地らしくて良いなって思ってね。それであの、取材させていただいて、巡業のバスに乗せていただいて。自分が今までやったことのない世界を描いてみたかったのね、うん。
 木村:これはじゃあ自分の知らない世界でしたけれども、この『深夜にようこそ』はコンビニエンスストアが……
木村:これはじゃあ自分の知らない世界でしたけれども、この『深夜にようこそ』はコンビニエンスストアが……
山田:そうそう、コンビニっていうのは僕は知らなかったのね。
木村:あ、これも、知らなかったけど……
山田:知らなかったです。それであの自由が丘のなんか外れみたいなところで、僕はアパート借りて仕事してた時期があって、それはあの大体仕事して泊まる風には思ってなかったんです。いつもこう通勤するみたいにね。ところがこう熱中して書いてたら、深夜になっちゃってたわけ。それでものすごくお腹が空いてきてね(笑)。で、何にもないんですよ。一応冷蔵庫はあるんですけど、何にも買ってない。それで外へ出たけどもシーンとしてて。これで俺は遭難しちゃうぞとか思って(笑)、歩いてたら道の向こうにパーッと道に灯りがある。何だろうと思って行ったらコンビニがあったわけですよ。もうその頃はコンビニって結構あちこちにあったんだけど、僕は関心がなかった。で、中入ったら、何でもあるじゃないですか。もう感激してね。これ素晴らしい!と思ってね、大山(勝美:当時のTBSプロデューサー)さんに「あのコンビニ書きたい」って言ってね(笑)。
木村:へぇー。
山田:で、大山さんとあっちこっちに取材で歩きましたよ。高島平とかね。
木村:あ、じゃこの『深夜にようこそ』って、「深夜にようこそ、山田太一さん」ってことだったんですね。
山田:そうそうそう(笑)。
木村:(笑)一番最初はそうやってドラマって生まれるんですねー。
山田:取材していくとね、結構大変でね。24時間やってるってことの大変さはホントにビックリしました。だからそういうことも書きましたけれどもね。
語り:さらには、楽曲からドラマを発想することも。『悲しくてやりきれない』は、ザ・フォーク・クルセダーズの名曲ですが、山田さんはおおたか静流さんが歌うこの曲を聴いて、アイデアを思い付いたそうです。
● 『悲しくてやりきれない』(1992年)について 木村:この『悲しくてやりきれない』は、主題歌のおおたか静流さんの歌がまたすごーく良かったですが、こういうのは……
木村:この『悲しくてやりきれない』は、主題歌のおおたか静流さんの歌がまたすごーく良かったですが、こういうのは……
山田:そうそう。なぜ買ったんだろうかよく憶えてないんだけど、おおたか静流さんのアルバムを買って聴いてて「悲しくてやりきれない」が素晴らしいと思ったの。それで高橋一郎さんっていう演出家に電話して、「もうこれが流れるドラマを書きたい」って言ってね。それで高橋一郎さんもすぐ聴いてくれて、「この芝居これ行きましょう」って、おおたか静流さんに電話したら、「どうぞやってください」って言うんで。
ホントはあの、北山修さんたちのところが歌ってるんですよね。サトウハチローさんの作詞だから相当昔の作品ですよね。だけどおおたか静流さんの歌はね、僕、とっても素晴らしいと思ってるのね。おおたか静流さんのコンサート行ったりしてね、ええ。それで話考えていったのね。みんなでなんだか悲しくてやりきれないという状況になって、そこに歌が流れるっていうのを目指したわけね。
木村:へぇー、歌最初にありきのドラマだったんですね。
山田:そうなんです。
木村:この次の『丘の上の向日葵』は、山田さんの小説だと……
山田:これは朝日新聞の連載小説でね。そうです。これは僕は、小説はあまりドラマにならないんじゃないかなとか思って、勝手に書いてたんですけど、これはね、なんか僕、なるような気がしてきたのね。
語り:男女の友情は成立するかをテーマに、平凡な中年男性と美しい人妻の関係を描いた『丘の上の向日葵』。東芝日曜劇場が、それまでの一話完結型から連続ドラマスタイルに変わった1作目として、山田さん原作の小説がドラマ化されました。
● 『丘の上の向日葵』(1993年)について 木村:あの、小説と脚本って、お書きになっててまったく違うものですか?
木村:あの、小説と脚本って、お書きになっててまったく違うものですか?
山田:僕はね、小説を書いてるときは脚色するとか役者とか考えないです。一切考えないで、小説を書きます。まあでも結果的にはね、こうやってテレビにさせていただいたものもいくつかはありますけれども。
木村:あの、ミステリーとか刑事物っていうのはお書きにならない……ですか?
山田:うん、つまりうまい人いっぱいいるでしょ。そこへ参入してもかなわないだろうと思ってね(笑)。まあ、長所と欠点っていうのはみんな持って商売してるわけですよね。何もかもに長じようっていうのもおかしいですよね。やっぱりあの……そりゃやればやれるかもわかんないけれども……まあそれはうまい人たちにお任せしようと……
木村:任せて……(笑)
山田:僕は片隅で(笑)細々とやって……
木村:いやあ、細々とだなんて……
語り:人生に一つの区切りをつけ、これからの人生を模索する初老の男女三人の心の襞を繊細に描いた『遠い国から来た男』。山田太一さんの真骨頂とも言える、人の心のかすかな移ろいを優しく捉えた名作です。
● 『遠い国から来た男』(2007年)について
山田:仲代さんがとっても良かったですね。それから杉浦直樹さんの最後の作品になってしまったんですね。それでとっても「あ、あんときやって良かった」と思いましたですねぇ。杉浦さんとは本当に長いことの付き合いで……
木村:そうですよね、たくさん……
山田:(フィルモグラフィのフリップを指して)この前からのつきあいというかな、あの、助監督に入社してすぐの映画で……杉浦さんは知らないんですよ、そういうの……あの、僕は新米の助監督でしたから(笑)。でもそのときからずっと付き合っていただいて。まあ、最後のドラマを書けたっていうことは、ものすごく悲しいけど、まあ、最後やらしていただいて良かったとは思います。
木村:まあ、2週に渡ってお話しを伺ってまいりましたが、最後に山田さんにお伺いしたいんですが、山田さんにとってテレビとは何でしょうか?
山田:まあ何だってそうだけど、どんどん変わりますね、テレビだってそうだけど、人生だってそうだけど(笑)。時間って本当に生きててどんどん動くからじっとしてることはないですよね。幸福も絶望もテレビも(笑)じっとしてないですね、うん。だからあの、こうあるべきだなんていうふうに思ったりしてるとすぐ、肝心なものは動いてっちゃうっていうねえ。だけど先読みをしすぎる、っていうことは良くない。あの、未来に適応しよう未来に適応しようと思いますよ。僕もちょっとそういう傾向がある(笑)。現在に適応しないでね……
木村:現在を壊していこうとなさってる作品が多いですからね(笑)……
山田:そう、未来に未来に適応しようと(笑)……。うん、それだから人のことは言えないけども、未来にあまり適応しすぎてもいけないなっていうかな、まあこの年になったせいでもあるけども……うん、あの、なるべく今を生きたいと思いますけどね。
2013年9月記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
山田太一作品・竹林軒批評リンク集
ドラマ
TBS系
● 木下恵介アワー
『3人家族』と『二人の世界』
『3人家族』(1)~(13) (1968年・木下恵介プロ、松竹、TBS)
『二人の世界』(1)~(26)(1970年・木下恵介プロ、松竹、TBS)
『たんとんとん』(1971年・TBS)
『それぞれの秋』(1)~(15)(1973年・TBS、木下恵介プロダクション)
『同棲時代』(1973年・TBS) 『真夜中のあいさつ』(1974年・TBS)
『真夜中のあいさつ』(1974年・TBS)
『なつかしき海の歌』(1975年・TBS)
『沿線地図』(1)~(15)(1979年・TBS)
『想い出づくり。』(1)~(14)(1981年・TBS)
『輝きたいの』(1)~(4)(1984年・TBS)
『深夜にようこそ』(1)~(4)(1986年・TBS)
『あなたが大好き』(1988年・TBS)
『ハワイアン ウエディング・ソング』(1992年・TBS)
『春の惑星』(1999年・TBS)
● 日曜劇場
『日曜劇場 風前の灯』(1974年・TBS)
『日曜劇場 縁結び』(1974年・TBS) 『日曜劇場 終りの一日』(1975年・TBS)
『日曜劇場 終りの一日』(1975年・TBS)
『日曜劇場 秘密』(1975年・TBS)
『日曜劇場 三日間』(1982年・TBS)
『日曜劇場 それからの冬』(1991年・TBS)
『おやじの背中』(7)(2014年・TBS)
『再会』(2001年・中部日本放送)
『旅の途中で』(2002年・中部日本放送)
『いくつかの夜』(2005年・中部日本放送)
NHK
『男たちの旅路 第3部「シルバー・シート」』(1977年・NHK)
『タクシー・サンバ』(1)~(3)(1981年・NHK) 『ながらえば』(1982年・NHK)
『ながらえば』(1982年・NHK)
『冬構え』(1985年・NHK)
『今朝の秋』(1987年・NHK)
『夕暮れて』(1)~(6)(1983年・NHK)
『友だち』(1)~(6)(1987年・NHK)
『春の一族』(1)~(3)(1993年・NHK)
『秋の一族』(1)~(3)(1994年・NHK)
『夏の一族』(1)~(3)(1995年・NHK)
『家へおいでよ』(1)~(6)(1996年・NHK)
『鳥帰る』(1996年・NHK)
『風になれ鳥になれ』(1)~(3)(1998年・NHK)
『いちばん綺麗なとき』(1999年・NHK)
『キルトの家』(2012年・NHK)
『ナイフの行方』(2015年・NHK)
テレビ東京 『せつない春』(1995年・テレビ東京)
『せつない春』(1995年・テレビ東京)
『奈良へ行くまで』(1998年・テレビ東京)
『小さな駅で降りる』(2000年・テレビ東京)
『香港明星迷』(2002年・テレビ東京)
『本当と嘘とテキーラ』(2008年・テレビ東京)
フジテレビ
『早春スケッチブック』(1983年・フジテレビ)
『時にはいっしょに』(1)~(11)(1986年・フジテレビ)
『秋の駅』(1993年・フジテレビ、福島テレビ)
『大丈夫です、友よ』(2017年05月)(1998年・フジテレビ)
『旅立つ人と』(1999年・フジテレビ)
『この冬の恋』(2002年・フジテレビ)
『やがて来る日のために』(2005年・フジテレビ)
『星ひとつの夜』(2007年・フジテレビ)
『よその歌 わたしの唄』(2013年・フジテレビ)
日本テレビ
『季節が変わる日』(1982年・日本テレビ)
『ちょっと愛して…』(1985年・日本テレビ)
『遠まわりの雨』(2010年・日本テレビ)
テレビ朝日
『終りに見た街』(1982年版)(1982年・テレビ朝日)
『終りに見た街』(2005年版)(2005年・テレビ朝日)
『時は立ちどまらない』(2014年・テレビ朝日)
『五年目のひとり』(2016年・テレビ朝日)
映画 『異人たちとの夏』
『異人たちとの夏』
シナリオ
『幸福駅周辺・上野駅周辺』
『午後の旅立ち』
『あこがれ雲』
エッセイ
『光と影を映す』
『寺山修司からの手紙』
『その時あの時の今 私記テレビドラマ50年』
『S先生の言葉』
『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと』
2019年5月まとめ
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『二人の世界』(1)~(26)(ドラマ)

二人の世界 (1)~(26)(1970年・木下恵介プロ、松竹、TBS)
演出:木下恵介、川頭義郎、横堀幸司
脚本:山田太一
音楽:木下忠司
出演:竹脇無我、栗原小巻、あおい輝彦、山内明、文野朋子、東野孝彦、三島雅夫、小坂一也、水原英子、太宰久雄、武智豊子、矢島正明(語り)
人に歴史あり、店に歴史あり
 山田太一初期の傑作『二人の世界』を12年ぶりに見る。前にもレビューを書いており、しかも内容がよく書けているため今回は良いかと思っていたが、やはり印象が強く、何か書いておくべきと感じる。
山田太一初期の傑作『二人の世界』を12年ぶりに見る。前にもレビューを書いており、しかも内容がよく書けているため今回は良いかと思っていたが、やはり印象が強く、何か書いておくべきと感じる。
何よりも善意の人々が多く出てきて心地良い。最近『スカッとジャパン』に出てくるような危ない奴に出会うことが続いて、嫌な気持ちが続いていたんだが、このドラマを見て少し気持ちが和らいだ。それにこのドラマにもちょっと危ない奴が出てきて、主人公も同様に気分が落ち込んだりしているのが、また共感を呼ぶ。前にも言ったように、ナレーションがやたら多いとか、今の時代から見るとところどころ違和感があるが、しかし素晴らしいセリフも随所に散りばめられていて、山田太一の面目躍如と言える作品に仕上がっている。全編フィルム撮影されているため、70年のカラー作品でありながら、今でも残っていたというラッキーな作品でもある(この頃ビデオで撮影された作品は、多くが失われている)。かつて改革開放前の中国でも放送されたことがあるらしく、栗原小巻は中国でも人気があるとか(竹林軒出張所『中国10億人の日本映画熱愛史(本)』を参照)。もちろんこのドラマの栗原小巻、それから竹脇無我は非常に魅力的である。
少し前に放送された『3人家族』と同じようなスタッフ、キャストで、主人公の2人の役回りも同じなんで、最初は恋愛話かと思って見ていると、第6回で突如、恋愛話が終わってしまって、その後、一体どういう方向に進むのか気になって見続けるというドラマである。前も書いたが、子供の頃、親が一生懸命このドラマを見ていて、だが僕はこの時間帯(21時から放送だったと思うが)すでに寝る時間で、そのためにテーマ曲だけが耳に入っていた。あのあおい輝彦のテーマ曲がまたメロウで良いのである。そのときも子ども心に恋愛ドラマだと思っていたのだ。
音楽と言えば、音楽監督は木下恵介の弟、木下忠司で、音楽もあまり目立たないが非常に良い仕事をしている。ところどころ水戸黄門風になるが、それは同じ作曲家だから仕方ない。
登場人物で言えば、物わかりの良い麗子の父(山内明)とコックの沖田(三島雅夫)が、出てくるのが楽しみになるような存在で、非常に魅力的である。あおい輝彦は『3人家族』同様、好人物を演じているが、今回は『3人家族』よりやや引いた位置付けという感じである。
また、冒頭のタイトルバックが非常に上品なのも良い。ジャン・コクトーのリトグラフが部分部分映されるだけの映像だが、落ち着きがあって、心が安まる。テーマ曲と合わせて、本編に対する期待感を膨らませるような役割も果たしている。
今回、何本かずつ連続で見たために、途中、少し気が抜けたような気がした回もあったが、ストーリー上それなりにいろいろと困難が出てきて、いろいろな人々の善意で助けられるという展開は、適度な緊張感が続いて、連続ドラマとしてはこれ以上ないくらいよくできていると思える。気持ちが暗くなって人を信用できなくなったらもう一度見ようかと思えるような「素敵な」ドラマである。
せっかくなので、すべての回のストーリーを簡単にまとめておこうと思う。
★★★★
参考:
『遙かなり 木下恵介アワー』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』
『テレビがくれた夢 山田太一 その1』
竹林軒出張所『「3人家族」と「二人の世界」(ドラマ)』
竹林軒出張所『3人家族 (1)~(13)(ドラマ)』
『夏の一族 (1)〜(3)(ドラマ)』
竹林軒出張所『中国10億人の日本映画熱愛史(本)』
主な登場人物
二郎(竹脇無我)
麗子(栗原小巻)
麗子の弟、恒雄(あおい輝彦)
麗子の父(山内明)
麗子の母(文野朋子)
レストランのコック、沖田(三島雅夫)
二郎の友人、関根(東野孝彦)
第1回から第6回は出会い・恋愛編。
第1回
アルマンド・ロメオのコンサート会場。チケットを持っていないにもかかわらず一番高い料金を払うから中に入れてくれないかと支配人に無茶な申し出をするサラリーマンの二郎(竹脇無我)。ここで、同じような申し出をしに来た麗子(栗原小巻)と出会う。結局2人ともコンサートには入れなかったが、意気投合し、その夜、赤坂のあるレストランで一緒に食事をする。ここのコック(三島雅夫)とも親しくなる。2人は翌日も会う約束をする。
第2回 翌日2人は昼食を共にする。その場で二郎は、麗子に特別なものを感じていることから真剣に付き合いたいと麗子に言い、麗子も賛同する。だが麗子には婚約者がいた。しかしその日のうちに、麗子はその婚約の解消を相手に伝える。麗子の弟(あおい輝彦)、父母(山内明、文野朋子)が心配して動揺する。
翌日2人は昼食を共にする。その場で二郎は、麗子に特別なものを感じていることから真剣に付き合いたいと麗子に言い、麗子も賛同する。だが麗子には婚約者がいた。しかしその日のうちに、麗子はその婚約の解消を相手に伝える。麗子の弟(あおい輝彦)、父母(山内明、文野朋子)が心配して動揺する。
第3回
数日後の土曜日の夜、2人は会って、遅くまでデートする。麗子の帰りが遅くなったため、父母が心配し麗子を責める。麗子は二郎のことを話し、知り合ったのは5日前だが「結婚しても良いと思っている」と語る。近いうちに父母に二郎を会わせることを誓う。ちなみに二郎は会社の寮で一人暮らし。同僚の関根(東野孝彦)に麗子のことを打ち明ける。翌日、父から二郎の職場に連絡が入り、次の日に麗子の家で面会することを約束する。
その日のうちに麗子の弟の恒雄が会社まで出向き、姉と別れろと迫る。
(物わかりの良い父のセリフ「(娘のことが)長年一緒の家にいた仲だ。(帰宅が遅くなって)気になったって仕様がないだろ」が良い。『夏の一族』にも似たセリフがあった。)
第4回
翌日、二郎が、麗子の家にあいさつにやってくる。良い雰囲気である。
第5回
 第4回の続き。麗子の家。良い雰囲気だったが二郎が(出会って6日であるにもかかわらず)結婚したいと切り出したために急に空気が冷え込む。父母は早すぎると言うのである。麗子と二郎を責める。返事は今すぐできない、あらためて返事すると言われ、二郎は暗い顔で家を後にする。その後、父母は麗子を「世間知らず」と責めるが、麗子も父母に「気持ちは変わらない」と訴える。
第4回の続き。麗子の家。良い雰囲気だったが二郎が(出会って6日であるにもかかわらず)結婚したいと切り出したために急に空気が冷え込む。父母は早すぎると言うのである。麗子と二郎を責める。返事は今すぐできない、あらためて返事すると言われ、二郎は暗い顔で家を後にする。その後、父母は麗子を「世間知らず」と責めるが、麗子も父母に「気持ちは変わらない」と訴える。
二郎の帰り道、弟の恒雄が後をつけてきて話があると切り出す。二人でとあるバーに入る。恒雄は別れろと迫るが、二郎は真剣だと訴える。恒雄はその後、酔っ払ってベロベロになり、二郎に介抱されてしまう。
二郎の田舎の家族も、二郎の兄は、何だか癪だ(弟が東京でいい目を見ていることに少しひがみがある)が、父母は賛成という風景。
ところが、その後いきなり結婚披露宴のシーンに移る。「細かないきさつはもう十分だろう。結局二人は思い通りにしたのである。三ヶ月経った、晴れた冬の日曜日であった。」というナレーションが入る。そして無事に披露宴が終わる。
(当初、恋愛にまつわるあれこれが最後まで続く恋愛ドラマだとばかり思っていたのだが、このナレーションでそうでないことが明らかになる。)
第6回
二郎と麗子、新婚旅行から帰る。喧嘩したようで、雰囲気が悪い。だがさすが新婚、その日のうちに仲直りする。
第7回から第16回までは新婚・転職編であり、次の開業編への導入。
第7回
新婚生活は、麗子にとっては、夜遅い夫を待つというもので、砂を噛むような味気ない面もあった。一方二郎は、関根と共に、新しい合成樹脂プラントの輸出権を得るという非常に大きな仕事に関わることになる。非常に忙しくなるが、その中でも時間を割いて、平日の夜、2人で外食することになる。店は、初めてのデートのときに行ったあの赤坂のレストラン。ここであのコック、沖田にあいさつし、結婚したことを知らせる。沖田に大歓迎され、ボトルワインまでおごってもらう。(このコックが、見ていて楽しくなるようなキャラクターで、登場するのが楽しみになる。)
最後のナレーション「甘い、思い出しても懐かしい一夜であった。しかしその一夜は、そのときの二人には思いもよらぬほどの深い意味を潜めていたのであった。」
第8回
新婚生活。麗子は幸福を感じている。かつての麗子のフィアンセが訪れたり、二郎の友人の関根が飲みに来たりする。一方二郎は、手がけていた仕事が結局他の会社に渡り駄目になってしまったのだった。
最後のナレーション「その仕事の失敗は、二郎たちのミスではなかった。重役たちの決定の甘さに原因があった。しかし原因とかかわりなく、それが二人を思いがけない運命に導いていくのである。」
第9回
二郎と関根が、重役の代わりに仕事の失敗の責任を負わされ、花形の営業部から総務部へ異動させられることが決まる。関根は、嫌気がさして会社を辞め、作曲家になるべく、修行することにする。一方二郎は、関根みたいな夢もない上、嫌なことがあったからといって辞めてしまうのは本意ではないということで、異動を受け入れることにする。二郎は麗子に異動になったことを告げる。二郎は、異動になった後、仕事に張り合いを感じることができず、砂を噛むような毎日を送る。辛い思いを共有したいと思う麗子だが、二郎は弱みを見せたくない。二人の気持ちがすれ違う。
最後のナレーション「しかし二人は、離れて立ったままであった。会社での辛い思いを二人で抱き合って慰め合うのではあまりに屈辱的ではないか、という思いが二郎を麗子に近づけなかった。」
第10回
総務の仕事は単純作業。麗子は、二郎の左遷について母に言えない。二郎は家では明るく振る舞う。「なぜ辛さを見せないのか」と思う麗子。
夜、近所にできたというスナック(軽食やアルコールを出す喫茶店)に二人で出かける。スナックは若い夫婦が二人でやっていた。良い感じの店だと二人で話し合う。
最後のナレーション「何気ない土曜日の夜のひとときであった。しかし、そこで見た若夫婦の働く姿が思いがけなく強い印象を残した。時が経って、その印象が一つの力となるのである。」
第11回
家で少し言い合いをする二郎と麗子。
二郎「慰めてもらってニヤニヤ会社に行かれるかい」、麗子「本当に今の仕事が不満なら他にどういう生き方でもできる」、二郎「甘っちょろいこと言わないでくれよ。辞めりゃ簡単さ。不満なら辞める、また辞める、だけどどこの会社に行ったってそう変わりゃしないんだ。だから我慢してるんじゃないか、生活ってのはそういうもんだ」、二郎「僕だっていろいろ考えてるんだ。青臭いこと言わないでくれよ」。
翌日、麗子は一人で近所の例のスナックに行って少々和む。夜、二人で浅草で外食して仲直り。二郎の大学の入学式の後、父と飲んだという店(この店の話は山田太一のエッセイに出てくる。脚本家自身の経験が反映している)。二郎「夕べ言ったことを何遍も考えた。辞めないでいる理由もない。もう少し自分の世界を広く考えたい」などと言い、転職について考えると言う。麗子も賛同する。
第12回  結局、二郎は会社を辞めることに決める。麗子は父にそのいきさつを説明する。辞めたら生活が厳しくなるかも知れないため、自分も仕事をしたいので仕事を紹介してくれないかと依頼する。
 結局、二郎は会社を辞めることに決める。麗子は父にそのいきさつを説明する。辞めたら生活が厳しくなるかも知れないため、自分も仕事をしたいので仕事を紹介してくれないかと依頼する。
二郎、友人の関根にも決心を告げる。関根は、商売を始めたらどうだなどと軽口を叩く。二郎、その言葉が少し引っかかって、商売について考えるようになる。麗子はこの話を聞いて、小さい店を持って二人で働けたら素敵だなどと言う。
翌日、二郎は屋台でラーメンを食べ、屋台の店主(加藤嘉)の話を聞く。この店主も元勤め人で脱サラして屋台を始めたという。店主「脱サラしたときの自由だという気持ちが忘れられない」。脱サラして商売を始めることにリアリティが出てくる。二郎「一発ドカンと何かやりたくなったな」。このとき商売を始めることをはっきり決意する。翌日、麗子にそのことを伝える。開業資金について具体的に考えるようになる。二郎「親父に相談しようと思う」。麗子「時間かけて少しでも良いお店にしましょう」。
最後のナレーション「威勢の良い決心の仕方ではなかったが、二人の前にまったく見当の付かない新しい世界が開け始めていた。期待と不安とが二人の間を流れた。静かな朝であった。」
第13回
二郎、実家に帰り、会社を辞めてスナックを開店したいということ、金を貸してほしいということを伝える。兄、一郎はいきり立って金はないと言い、父も何も言わない。だが翌日帰郷する段になって、父が定期貯金が近いうちに満期を迎えるのでその200万円を貸すと言う。ただし一郎の手前があるため利子を取ると言う。兄は帰り際に二郎を呼び、50万円無利子で貸すという。(兄貴、頑固だが良いところがある。)
最後のナレーション「250万の借金と自己資金50万、あわせて300万円の目安は付いたが、それだけでスナック開店は無理であった。しかし、漠然とした転職という希望から、もう一歩具体的な領域に足を踏み入れたのである。そのことが、二人を明るくさせていた。」
第14回
工作機械の会社(社長はタコ社長、太宰久雄)で勤めを始めた麗子。二郎は、退社後、スナックの実務について教える学校に1カ月間通うことにする。
二郎、会社を辞めて新しい商売を始めるということを、麗子の父母に直接会って話す。具体的なプランが決まったら教えてくれと話す父。プランが良ければ金を出すとまで言う。(物わかりの良い父である。)
最後のナレーション「二郎は、麗子の両親の目に自分がどのように映ったかがわかるような気がした。不確かな夢を追う男。しかし絶対に成功してみせる、見ていて欲しいと二郎は思った。」
第15回
友人の関根が自宅にやってくる。習ったばかりの料理で関根を接待する二郎。関根はその後、金を無心するつもりでここに来たと言う。音楽の師匠がアメリカに行ってしまい生計を立てていた仕事ができなくなったというのだ。二郎は侠気を出して5万円貸してしまう。後でその金額のことで二郎と麗子は喧嘩する。
翌日も喧嘩の状態が続くが、夜、二郎は上機嫌で帰ってくる。来月会社を辞めてしまい、来月から1月間、他のスナックに見習いに行くことにしたと言う。自然に仲直りしてしまう二人。失恋して遊びに来ていた恒雄は、一人取り残された形になる。
最後のナレーション「二人の世界が大きく変わろうとしているところだった。取り残されて恒雄は孤独の中にいた。」
第16回
二郎、ついに会社に辞表を出す。退職の日、二人だけでささやかに自宅でパーティ。
(恒雄の恋愛のエピソードが並行して進んでいるが、これについては省略)
最後のナレーション「新しい世界へ踏み出す二人にしては呑気すぎる夜であったが、ともあれこれが、二郎のサラリーマン生活、最後の夜であった。」
第17回から第26回までが開業・奮闘編。
第17回
二郎、スナックの見習い勤めを始める。麗子、好奇心から見に行く。二郎、カウンターに入って、それらしく立ち振る舞っている。ホットケーキまで作って麗子に出す。二郎はそれなりに自信をつけている。
二郎、物件探しを始める。
第18回 二郎が目星をつけた物件を、麗子、麗子の父母が、二郎と一緒に見に来る。
二郎が目星をつけた物件を、麗子、麗子の父母が、二郎と一緒に見に来る。
この物件に一端は決めるが、その後、父が、自分も100万円出資するから、やはり高くてももっと良い物件を探してみないかと言う。「君たちが新しいことを始めるのを見ていると、自分も肩入れしたくなる。だから無利子、無期限で100万円貸す。君たちの夢にかけたい、仲間に入れてもらいたい」と言ってくれる。(良い義父である)
あらためて店探しを始める二人。そんな折、恒雄が新しい物件を探してくる。現在スナックで、店主がスナックを辞めるから貸しに出すという。そのために居抜きで借りられる。条件は良く予算的にも何とかなる。結局ここに決めるが、前オーナーがスナックを辞めるということが気にかかって、近所のおばさんに話を聞く。何でもこれまでこの物件を借りてきた人々の夫の方が次々に不幸に見舞われてきたという不気味な事実が判明。今のオーナーも夫が入院して仕事ができなくなったという。家族会議の結果、しかるべき神事を行うなどして、この物件を借りようということになる。
最後のナレーション「こうして店が決まった。若い二人には似合わなかったが、占い師の言うとおりにした。女の怨みを鎮めるという神社の神主を招いたのである。これから店を直し、開店の支度である。いよいよ二人の新しい人生であった。」
第19回
店の改装、開店準備が進み、いよいよ翌々日開店という運びになる。二郎の兄が、開店祝いで上京する。良い店だと祝ってくれる。
翌日、関根がやって来て、借金を返す。仕事が順調に進み出したことも報告。夜、新しい店に関係者を呼んで、開店パーティを開く。
いよいよ開店の日を迎える。朝早く目を覚ましてしまう二郎。いろいろと考えてしまう。
最後のナレーション「結局7時半には店へ来ていた。あと3時間半で開店である。二人は黙りがちに、しかしクルクルと働きながら、新しい世界の出発の時を待った。」
第20回
開店初日風景。最初の客は変な若者で、コーヒーを頼むが結局何も飲まずに出ていく。客は昼頃から大勢訪れ、昼食時が終わるとめっきり客足が減る。客の流れが初めてわかる。恒雄が連れてきた学生たち、家族連れなど、いろいろな客がやってくる。夜は夜で、一人で入ってくる客が多く静かになる。最後の客は、読書している、感じの良い客(小野寺昭)である。こうして初日の営業が終わった。
最後のナレーション「開店の日の売上は、20,530円。予想以上の成績である。このまま順調にいけば、借金もそれほどかからずに返せるかに見えた。明るい夜であった。胸の膨らむ1日であった。」
第21回
翌日の昼間、麗子の父が店にやって来る。麗子は、テレビかステレオを入れるという話になっているという話を父にする。父は、テレビを入れないという選択肢もある。客がテレビを入れてくれと言っても、すべての客に対応することはない。客本位になるのも良いが店がお客さんを選ぶことも必要じゃないか。自分の店はこう行きたいという個性みたいなものが欲しいじゃないかと言う。(良いセリフである。)
夜、近所の若者たちがやって来て大きな声でギャンブルの薄っぺらい会話をしている。うるさいため、昨日の読書の客も早々に帰ってしまう。しかもこの若者たち、支払をツケで頼むと言う。二郎は受け入れようとするが、麗子が切れてしまい、うちは掛け売りはお断りしていますと言って追い返してしまう。
麗子「店の方で客を選ぶ権利がある、あんな人にニコニコするのはいやだ、店の方針をはっきり決めて、格みたいなものを作った方が良い」と二郎に言う。そんなことじゃやっていけないと二郎。麗子「近所を見てみたところ、あまり良いものを食べる場所がない。良いものを出すなど、思い切って店の特色を出してみたらどうだろう」と言う。二郎は、「甘いことを言う」と言って怒る。どうしてそんなことが我々にできるのか、そんなことを考えるのは5、6年早いと言うのだ。
その後、開店してから1カ月経った。なんと10軒と離れていない近所にスナックができることがわかる。テーブルが5、6個あり、しかも大きなクーラーを入れ、ジュークボックスも置くという。
新しい店の存在が気になる二郎、あのレストランのコック、沖田に、新しい料理について相談してみることにする。店の特色を出すという麗子の提案について、考えてみようというのである。
最後のナレーション「なぜか、赤坂のレストランで「料理だけが生きがいだ」と言ったあのコックの姿が突然蘇って、二郎を呼ぶのであった。あの屈託のない楽しげな姿。」
第22回  二郎、赤坂のレストランを訪れて、コックの沖田と話をする。何かこれはという一品を出したいからアイデアがあったら教えてもらえないかと言う。沖田は快諾する。
 二郎、赤坂のレストランを訪れて、コックの沖田と話をする。何かこれはという一品を出したいからアイデアがあったら教えてもらえないかと言う。沖田は快諾する。
二日後、沖田が店を訊ねてくる。しかも近所の店のリサーチ済みで、二郎と麗子はいたく感心する。
翌日の夜、店の営業中、近くに新しくできるスナック「うぐいす」の若い店主、本木(小坂一也)とその父親(内田朝雄)がやって来てあいさつする。父親の方はドスが利いた感じ。「うぐいす」の方は、開店に備えて、店先で大々的に宣伝活動。サービス券を配付したりする。
その後、再び沖田が、食材を持って開店前にやって来る。美味しいカレーを伝授すると言う。いろいろと考えたがスナックに適した一品というとやはりカレーかということになったと言う。
最後のナレーション「沖田は楽しげに新しいメニューの準備を始めたのであった。」
第23回
沖田がカレーを実際に作ってみると、非常に旨く、二郎は感心しきりである。麗子は「今日仕込んだカレーを売るのが嫌になった」とまで言う。また沖田はハンバーガー弁当のアイデアも用意し、そのレシピも授けてくれる。沖田は、こうして頼られるのが嬉しいと語る。(沖田の善意が気持ち良い。)
ナレーション「その日の6時に新しいスナックは開店した。流行歌を流し店のしつらえも俗悪で、住宅の多いこのあたりには似合わない気がしたが、客の入りは良かった。主人の客あしらいも慣れていて、競馬であろうと、野球、麻雀、競輪から女の話までやすやすと相手になる男であった。同じやり方で競っても二郎に勝ち目はなかった。自分は自分のやり方でやり通すしかない。とにかく明日からだ。ハンバーガー弁当とカレーライスで勝負するのだ。」
二郎と麗子、宣伝ビラを配ったりポスターを出したり広報活動をする。
当日、開店前に「うぐいす」の親子がカレーを食べさせてくれと言ってやって来て試食していく。昼時はいつものように満員だがカレーの評価はわからず。ハンバーガー弁当も7個売れただけで、少々ガッカリ。昼が過ぎるといつものように暇になる。ところが午後になって、ハンバーガー弁当を20個買いたいという、近所の会社勤めの女性が来る。昼買って食べたら美味しかったために社長が社員におやつとして出すと言い出したらしい。最初の反響。
翌日、沖田に報告しに行く。謝礼を渡そうとすると拒まれる。「あんたがたに喜んでもらえて、この10年の間で一番楽しい思いをした。これからも肩入れさせて欲しい」と言う。
最後のナレーション「ところがその翌日、商売敵の新しいスナックは、10円安いカレーライスとカツサンド弁当を売り始めたのであった。」
第24回
「うぐいす」の方は、マスターが客あしらいがうまく、しかもテレビを入れているため、若者のたまり場みたいになっている。二郎と麗子は、それに少し危機感を持っている。テレビを入れた方が良いんじゃないかと思う。開店前に沖田がやって来て相談に乗る。
「問題はあなたがたがそういう店にしたいかということだ。店の方針というものが大事であって、客に合わせていたら切りがない、こっちで客を選ぶ気でなくちゃ」と言う。「店が人生の舞台なんだから客の顔色でどうにでもなるようにしてはいけない。旨い料理で評判を取っていくつもりだったんだからそれで辛抱していかなくちゃ。無理して客に合わせたんじゃ店を開いた甲斐がない。」
さらに沖田、3人であちらの店に行ってみてカレーを食べてみようと提案する。結局3人で食べに行く。味は到底問題にならないことがわかる。沖田は後に「しかし不味かったねぇ」と言って大笑いする。「あんなものは競争にも何にもなりはしない。10円安くたって、そんなの問題じゃない。相手が繁盛してもそんなものは一時だ。味一本」。
その夜「うぐいす」の本木が、酔っ払ってやって来る。ビールを頼むが、昼間のことに文句を言い、突然二郎を殴りつける。捨て台詞を吐いて出ていく。
翌日開店前に、本木親子がやって来て謝りに来る。体面上謝ってはいるが、愚痴や脅迫めいたことまで口上していく。その日の午後、いつもなら客足の少ない時間帯に学生が20人ばかりやって来てカレーを食べた。昨日の騒動のときに店にいた客が、昨日の騒動を「カレーの味に嫉妬した同業者が嫌がらせに来た」という評判にして友人を連れてきたのである。
昼時の込み方が日増しに激しくなってきた。美味しいという評判が広がっているのがわかった。その後、とある新聞に店のカレーの記事が載る。
第25回
店は順調。
麗子が妊娠したことがわかる。思わず「困ったなぁ」と口走る二郎。これが原因で夫婦喧嘩になる。
第26回
麗子、つわりで店に立てないことが多くなる。恒雄が手伝ったりアルバイトのウェートレスを雇ったりする。人を使うことを考えなければならなくなる。
二郎と麗子、沖田を中華料理店に誘い、お礼をする。その場で沖田が、別の有名レストランから引き抜きの話があると言う。だが今さらレストランを移るより、むしろレストランを辞めて、二郎と麗子の店を手伝いたいと言う。あの店を手伝うことは、張り合いもあるしやりがいもある。今金銭面では不自由はないため、月給5万円でしばらく雇ってもらえないかと言う。「若い人が一生懸命働いてだんだん大きくなる、そういうのを手伝ってみたい」と言う。二郎、「願ってもないこと。あまり良い話なんで信じられない」と言って歓迎する。
二郎の実家の兄、父母が上京し、店を見に来る。その後、麗子の実家で麗子の両親を交えて、二郎と歓談。(大団円1。)
店では突然の貸し切りが入り、沖田が助っ人でやってきて腕を奮う。(大団円2。)
最後のナレーション「確かに何もかもがこれからなのである。何一つ終わったものはなく、二人の世界は明日に向かって開けていた。子供が生まれる。他人と一緒の仕事が始まる。レストランに変えていく計画がある。こうした物語の終わりこそ二人にふさわしいと私たちは思った。」
今までのいろいろなシーンが回想風に流れ、テーマ曲が流れる。(良いエンディングである。)
2018年10月、記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『沿線地図(1)~(15)』(ドラマ)

沿線地図(1979年・TBS)
演出:龍至政美、大山勝美、福田新一、片島謙二
原作:山田太一
脚本:山田太一
出演:岸惠子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子、真行寺君枝、広岡瞬、笠智衆、新井康弘、野村昭子、三崎千恵子、楠トシエ、岡本信人、風間杜夫
70年代屈指のドラマの1本
 これも、若い頃見てその後永らく見たかったドラマで、見たいと思うようになってから30年以上が経っている。ああそれなのにそれなのに、なかなか放送されることはなく、もう一度見たいという思いがあまりに強かったために、結局シナリオを読むことでお茶を濁していた。今回ついにCSのTBSチャンネルで放送されたんだが、過去TBSチャンネルに幾度かリクエストを出してきたこともあり、「やっと」の感が非常に強い。
これも、若い頃見てその後永らく見たかったドラマで、見たいと思うようになってから30年以上が経っている。ああそれなのにそれなのに、なかなか放送されることはなく、もう一度見たいという思いがあまりに強かったために、結局シナリオを読むことでお茶を濁していた。今回ついにCSのTBSチャンネルで放送されたんだが、過去TBSチャンネルに幾度かリクエストを出してきたこともあり、「やっと」の感が非常に強い。
さていよいよ今回見ての感想だが、期待に違わず、非常に内容充実で存分に楽しめた。前に見たときは学生だったために、子どもの側の視線だったように思うが、今回は大人の側の視線になっているのが興味深い。見る人の立場によって異なる感じ方を持てるのがこのドラマで、さまざまな視点で見ることができると言える。
卒業を数カ月後に控えた高校3年生の男女(真行寺君枝、広岡瞬)が通学途中で顔見知りになり、ありきたりの生活に見切りを付けることを決意して、駆け落ちするところから話が始まる。ただし、駆け落ちといっても恋愛感情があふれて思いあまってというものではなく、とにかくパターン化された人生を変えてみたいという思いからしたもので、駆け落ちというより共同戦線といったイメージが強い。そのあたりがそもそも異色である。
当然のことながら、2人の両親(岸惠子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子)は、かれらを家に連れ戻すためにあれこれ画策するんだが、子どもたちから突きつけられる真摯な思いは、親の方の価値観まで揺るがしてしまうというありさまで、親やその周辺にも影響が徐々に広がっていくという話である。
女生徒が秀才の男生徒に近付くことで話が動き出すが、そこからその影響が少しずつ波紋のように周囲に広がっていって、大人たちがそれに慌てふためきながら、価値観の転換を余儀なくされるところまで、ごく自然に話が展開していくのも秀逸で、これだけ違和感なく自然に話が展開するドラマもなかなかないんじゃないかと思う。いろいろな問題点が視聴者に突きつけられ、考えることが要求されるのも、この頃の山田ドラマらしい。なんせ第1回目の予告編で「皆さんも一緒に考えてください」というナレーションが入っていたくらいだ。
前も言ったように、今回は完全に親の立場でドラマを見ていたので、最低限高校は卒業した方が良いんじゃないかなどと思ったが、そもそも主役の2人はそういう考えに反発をもったわけで、もし自分の子どもがこういう風に家を出て行ったらいかんともしがたい。良い高校を出て良い大学を出て有名企業に入るという「ありきたりな生き方」にはまったく共感しないが、この2人の場合はかなり極端な生き方で、客観的に見ていると若気の至りにしか見えない。
しかしなんと言ってもこのドラマで一番面白かったのは、だんだん変な風になっていく親たちの生活で、世間の常識に対して今まで疑問を持たずに生きてきた人々が、少しずつ歯車を狂わせながら、自分の価値観に向き合うことを余儀なくされていく過程は圧巻である。同時期の『岸辺のアルバム』ほど有名ではないが、それに勝るとも劣らない(個人的にはあれを凌駕しているとさえ思う)傑作ドラマで、シナリオだけでなく、演出、キャストとも申し分ない。それからテーマ曲のフランソワーズ・アルディの『もう森へなんか行かない』も秀逸。ドラマ全体の雰囲気をテーマ曲だけで定義しているかのようである。今回見ることができて本当に良かったと思う。TBSチャンネルに感謝だ。TBSはDVDも出したら良いのにと思う。
★★★★
参考:
『テレビがくれた夢 山田太一 その2』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』
『昔のドラマ』

2013年11月、記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『今朝の秋』(ドラマ)

今朝の秋(1987年・NHK)
演出:深町幸男
脚本:山田太一
音楽:武満徹
出演:笠智衆、杉浦直樹、杉村春子、倍賞美津子、樹木希林、加藤嘉、名古屋章
「多少の前後はあってもみんな、死ぬんだ」
 1987年に放送された山田太一作の単発ドラマで、数々の受賞歴が示すように評価の高い作品。
1987年に放送された山田太一作の単発ドラマで、数々の受賞歴が示すように評価の高い作品。
一人暮らしのとある老人(笠智衆)が、50台になる一人息子(杉浦直樹)が末期ガンであることを知るところから話が始まる。息子を送る側になってしまった老人、先に逝く息子、それを取り巻く人々などをめぐる話で、家族について考えさせられる一本。山田太一によって提示される家族観は結構シビアで、うへっと思うようなセリフも出てくる。セリフの中でも特に秀逸なのが、自分の死が近いことを知った息子と父との言葉少なではあるが、重く、そしてウィットに富んだ会話。
父 「多少の前後はあってもみんな、死ぬんだ」
息子「(父を見る)そうですね……みんな死ぬんだよね」
父 「特別なような顔をするな」
息子「(苦笑い)言うなぁ、ずけずけ。しかしね、こっちはまだ50台ですよ。
お父さん、80じゃない。こっちは少しは特別な顔するよ(笑うが、涙が
あふれる)」
出演も笠智衆、杉村春子と小津安二郎作品を彷彿させるようなメンツで、内容も松竹大船調と言ってよい。小津映画の正当な継承者は山田太一だったのかと感じさせられる。息子役の杉浦直樹は山田ドラマの常連で、このドラマでも素晴らしい演技を見せる。
演出の深町幸男も、山田太一とよく組んでいる人で、山田脚本の魅力を余すところなく表現している。武満徹の音楽もドラマ展開を邪魔せず、それでいてさすが武満徹とうならせるような素晴らしいものである。ドラマのさまざまな要素が高いレベルで一体化し、独自の世界を形作っている。
80年代は山田太一の全盛期で、この頃は名声も高かったせいか、オリジナルのドラマをたくさん発表している。その中でも最高峰と言える作品で、特にセリフが光る傑作である。
プラハ国際テレビ祭大賞、第14回放送文化基金賞本賞、毎日芸術賞受賞
★★★★
参考:
竹林軒出張所『ながらえば(ドラマ)』
竹林軒出張所『冬構え(ドラマ)』
竹林軒出張所『旅立つ人と(ドラマ)』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』

2013年4月、記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『夏の一族』(1)~(3)(ドラマ)

夏の一族 (1)~(3)(1995年・NHK)
演出:深町幸男
脚本:山田太一
出演:渡哲也、竹下景子、宮沢りえ、加藤治子、藤岡琢也、柄本明、永島敏行、大野雄一、森本レオ、柳沢慎吾
結局『冬の一族』はなかった
 山田太一の『一族』三部作(『春の一族』、『秋の一族』、『夏の一族』)の最後の作品。このドラマはこれまで3回くらい見ていて、何度見てもセリフのうまさに感心する。それに複数のプロットを巧みに組み合わせた重厚な構成にも感心する。山田太一の最高傑作の1本と言える。
山田太一の『一族』三部作(『春の一族』、『秋の一族』、『夏の一族』)の最後の作品。このドラマはこれまで3回くらい見ていて、何度見てもセリフのうまさに感心する。それに複数のプロットを巧みに組み合わせた重厚な構成にも感心する。山田太一の最高傑作の1本と言える。
自動車会社の設計部門で長年設計に関わっていた中年男(渡哲也)が、ある日突然販売所(つまり売る方)に出向になった。名目的には出向ではあるが、実質的には肩たたきということで、それでも仕事にしがみついて、上司(藤岡琢也)のいじめにも負けずに真面目に取り組む……というのが1つのプロット。この男の家族は一見したところ割合平穏に過ごしているが、娘(宮沢りえ)は妻子持ちの男と付き合っているし、妻(竹下景子)は夫に多少不信感を持ちながら昔の恋人にしきりに誘われたりしていて、こちらも少々危ない感じ。さらにまた主人公がかかわる不登校の中学生、主人公を育てた血のつながりのない「姉」(加藤治子)などとの間にもサブプロットが発生して、かなりいろいろなストーリーが盛り込まれているが、これがまた実にうまいこと調和している。それぞれの人間関係に強い繋がりがあってそれが不自然ではないため、現実性があり、人間関係にリアルな安定感がある。そのためか構成に隙がないように感じる。
 先ほども少し触れたが、このドラマは特にセリフが優れていて、全3回のドラマのあちらこちらに名ゼリフが散らばっている。またそれぞれのキャラクターがもれなく非常に魅力的で、利害が絡んで嫌な面を見せたりしはするが、それでも人間らしさが出ていて、大変気持ちがよい。それぞれのキャストが良い仕事をしているのは今さら言うまでもない。
先ほども少し触れたが、このドラマは特にセリフが優れていて、全3回のドラマのあちらこちらに名ゼリフが散らばっている。またそれぞれのキャラクターがもれなく非常に魅力的で、利害が絡んで嫌な面を見せたりしはするが、それでも人間らしさが出ていて、大変気持ちがよい。それぞれのキャストが良い仕事をしているのは今さら言うまでもない。
ただ難がないわけではなく、特に第3回は、途中からオカルトが入って『異人たちとの夏』みたいになるのは、あくまでも嗜好の問題ではあるが、いただけないと思う。必然性があると言えばいえるし、これも「ブラザー軒」みたいな1つのエピソードと考えればよいのではあるが、そっち方向には持っていってほしくなかったと感じる。また第3回は、セリフで語るシーンが非常に多かった。ただそのセリフの内容にはインパクトがあるので、まったく飽きたりすることはないが、第1回、第2回がドラマとしてあまりによくできていたため、第3回はやや平凡な感じがしたのが残念。
とは言うものの、これだけの作品は、いかに山田太一といえど、そう何作も書けるものではないと思う。『今朝の秋』同様、日本のテレビドラマの最高到達点と言えるような作品であることは間違いない。
★★★★
参考:
竹林軒出張所『春の一族 (1)〜(3)(ドラマ)』
竹林軒出張所『秋の一族 (1)〜(3)(ドラマ)』
竹林軒出張所『風になれ鳥になれ (1)〜(3)(ドラマ)』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』
竹林軒出張所『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと(本)』
『今朝の秋(ドラマ)』
竹林軒出張所『異人たちとの夏(映画)』
2017年7月、記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『深夜にようこそ』(1)~(4)(ドラマ)

深夜にようこそ(1986年・TBS)
演出:大山勝美、高橋一郎
脚本:山田太一
音楽:池辺晋一郎
出演:千葉真一、松田洋治、名取裕子、松本伊代、冨士真奈美、柳沢慎吾、坂上忍、小林克也、加藤登紀子、山田吾一、角野卓造、風見章子、下元勉、志賀真理子
「そう」と「ああ」だけで絵になる千葉ちゃん
 1986年の放送時に見たドラマで、それから30年近くに渡って見たいと思っていたドラマ。このたび、やはりTBSチャンネルで放送されるはこびになったので、喜び勇んで見たのだった。
1986年の放送時に見たドラマで、それから30年近くに渡って見たいと思っていたドラマ。このたび、やはりTBSチャンネルで放送されるはこびになったので、喜び勇んで見たのだった。
前に見たときは、とにかく主人公、村田耕三の印象が非常に強く、彼を演じる千葉真一が「そう」、「ああ」などと言うセリフにまで魅力を感じたものだったが、今回見てもやはりそれは健在。非常に魅力的な主人公が登場する。どう見てもすごい遣り手の男が、コンビニ・バイトの新人として入ってくるというストーリーで、ちょっとしたミステリーが持続する設定もなかなか面白い。また、それをサポートする立場の松田洋治も、彼らしい頼りない学生を演じていてこちらも良い味を出している。このようにキャストはどれもことごとく魅力的なんだが、使われるエピソードがややウソっぽく、リアリティに欠ける。「10万人目の客」とか「強盗」のシチュエーションは、ちょっと首をかしげてしまう。テーマは割合明解で、気持ちの良いドラマなんだが、そういう部分が最後まで引っかかる。大人向けのおとぎ話ドラマだと思って見れば気にならないかも知れない。
アイドル時代の松本伊代が出る他、悲劇のアイドル、志賀真理子もチョイ役で登場。坂上忍は、同じ山田太一ドラマ、『時にはいっしょに』と同じような役回りを演じていた。
★★★☆
参考:
竹林軒出張所『時にはいっしょに(1)〜(11)(ドラマ)』
『テレビがくれた夢 山田太一 その2(ドキュメンタリー)』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』
2013年9月、記
上に戻る![]()
「竹林軒出張所」選集
『早春スケッチブック』(1)~(12)(ドラマ)

早春スケッチブック(1983年・フジテレビ)
演出:富永卓二、河村雄太郎
脚本:山田太一
出演:鶴見辰吾、岩下志麻、山崎努、河原崎長一郎、樋口可南子、二階堂千寿、荒井玉青
第1回〜第4回
見始めると目が離せなくなる
 今回、14年ぶりにこのドラマを見た。あれからもう14年も経っているのかと思う。さらに言えばこのドラマが作られたのが1983年で、ドラマが作られてから36年経っている。主人公の少年が1983年の共通一次試験を受けるという設定になっているが、僕もあの年に共通一次を受けている。83年の試験は1月15日に実施されたが、なんと成人の日とかち合っていたため、試験場に向かうバスから成人式の晴れ着を着た女性がたくさん目に付いた。当時20歳だった二浪の友人も、こういった人々を目にして、俺は一体何をしているのかと考えたなどと漏らしていた。
今回、14年ぶりにこのドラマを見た。あれからもう14年も経っているのかと思う。さらに言えばこのドラマが作られたのが1983年で、ドラマが作られてから36年経っている。主人公の少年が1983年の共通一次試験を受けるという設定になっているが、僕もあの年に共通一次を受けている。83年の試験は1月15日に実施されたが、なんと成人の日とかち合っていたため、試験場に向かうバスから成人式の晴れ着を着た女性がたくさん目に付いた。当時20歳だった二浪の友人も、こういった人々を目にして、俺は一体何をしているのかと考えたなどと漏らしていた。
この共通一次試験を目前にしているのが主人公の高三の少年、望月和彦(鶴見辰吾)だが、父(河原崎長一郎)と母(岩下志麻)が再婚同士で、共に連れ子(母に自分、父に妹)がいたという設定である。ただ結婚してからすでに10年経っているため、普通の家族との違いを感じることはほとんどない。そのため普通に高校生活を送り受験勉強に励んでいたのであるが、ある日突然、新村明美(樋口可南子)という美女が目の前に現れて、バイトしない?などと言ってかなり強引に少年を、実の父(山崎努)の元に引っぱっていくというふうにストーリーが展開する。大学入試直前にあれやこれやが起こるというのも、『沿線地図』や『岸辺のアルバム』を彷彿させる。
この実の父、沢田竜彦というんだが、目を病んだことがきっかけで写真家を引退し古い洋館に引きこもっているという状態で、社会との唯一の接点になっているのが明美であるという設定である。和彦も最初は抵抗を覚えていたが、その後何度か沢田の元に足を運ぶようになり、沢田の影響を受けるようになる。実の父、沢田が「ありきたりな人生」を否定的に捉えるような発言をし、それをきっかけに自分の生き方についても考えるようになって、あげくに、今の父についても物足りなさを感じるというふうに話が進行していく。これが第4回までの流れである。ちなみに実の父に影響を受けてしまった和彦は、共通一次試験をすっぽかしてしまう。沢田から起こった影響が望月の家に波風を立てていくというふうにこれから進む。
ドラマは、最初からグイグイ視聴者を引っぱるような展開で、特に樋口可南子が登場するあたりからは先が見えないサスペンスが始まり、目が離せなくなる。脚本家の豪腕にうなってしまう。また樋口可南子と岩下志麻が非常に美しいのもこのドラマの大きな魅力である。山崎努の演技も大きな見所で、涙と一緒に洟を垂らすなどなかなか見ることができない怪演である(『北の国から』で地井武男が同じような演技をしたことがあったが)。第4回の段階では、沢田の病気がまだ見えていない状況である。
★★★☆
第5回〜第7回
河原崎長一郎の演技にただただ関心
 最近、山田太一脚本のドラマがあちこちで再放送されていて、見るのが追いつかないくらいである。日本映画専門チャンネルで『真夜中の匂い』(これが楽しみ)、BS12では『早春スケッチブック』から『想い出づくり。』、NHKでも『男たちの旅路』が3本放送されるという具合。だが『想い出づくり。』や『男たちの旅路』は割合「ありきたり」な選択という感じもする。やはり日本映画専門チャンネルはこの分野では先行しており、面白いラインアップを提供してくれる。
最近、山田太一脚本のドラマがあちこちで再放送されていて、見るのが追いつかないくらいである。日本映画専門チャンネルで『真夜中の匂い』(これが楽しみ)、BS12では『早春スケッチブック』から『想い出づくり。』、NHKでも『男たちの旅路』が3本放送されるという具合。だが『想い出づくり。』や『男たちの旅路』は割合「ありきたり」な選択という感じもする。やはり日本映画専門チャンネルはこの分野では先行しており、面白いラインアップを提供してくれる。
ところで、この『早春スケッチブック』では、重病になった元カメラマン(山崎努)が、「お前らは、骨の髄までありきたりだ」などと怒鳴り散らして、普通に生きる人たちに揺さぶりをかける。考えてみれば大きなお世話で非常に身勝手な言動だが、今まで自身の生活を振り返ることなく漫然と生きてきた人たちは、こういった刺激に過剰に反応してしまう。こうして善良で小市民的な生活を送っている人の家庭に波紋が起こるというわけだ。
第5回から第8回では、このカメラマンが、主人公の家庭、望月家にまで入ってきて、(元恋人だった)妻(主人公にとっては母)と逢うことを求め(夫に対して「奥さんを貸してくれ」などと言う)、主人公の家庭の平穏な生活をかき乱す。
このカメラマン、沢田(山崎努)、主人公の家族に対して不快な言動を繰り返すが、その一方で、実は割合良い人みたいな側面も見せ、そのために主人公の少年(鶴見辰吾)とその母、それから育ての父と妹も少しずつ気を許していくそぶりを見せる。かと思えば突然豹変して、相手の気持ちをえぐるような嫌な言葉を発してきたりもする。普通の人々は、こういった言葉を不快に感じつつも、どこかで揺さぶられてしまう。特に主人公の育ての父は、現状肯定型の小市民的な生活を送る人で、沢田と好対照をなす存在。もちろんそういった小市民的な生き方を否定することはまったくできないのであって、「ありきたり」であろうが、長い目で見ればそちらの方が良いかもしれないし、そもそもどちらが良いとかいう問題でもない。
そういう小市民的な存在を巧みに表現しているのが河原崎長一郎である。この人、僕が子どもの頃からテレビでよく目にしていて、こういう小市民的な役が多かったという印象が僕の中にあるが、確認すると必ずしもそうではないようである。こういった小市民的な役は、山田太一のドラマ(『沿線地図』、『友だち』)ぐらいで、そうするとやはり、僕の中で山田ドラマの印象が非常に強かったということになるのだろうか。この河原崎長一郎、演技があまりにさりげなく影が薄いんでつい見過ごしがちだが、毎度毎度素晴らしい演技である。周辺の人間に対する気遣いや愛想笑いなど、市井の人物の表現がピカイチである。今回見ていて、すごい役者であることにあらためて気付き、ただただ感心した次第。なお、河原崎長一郎、妻役の岩下志麻と実はいとこ同士らしい(ウィキペディア情報)。
★★★★
追記:
第8回の最後で、元カメラマン、沢田の身体に変調が起こるため、ここからいよいよ収束に向かうということになりそうだ。
第9回〜第12回
そして大団円で終息に向かう 望月家に騒動をもたらしている元カメラマン、沢田(山崎努)の病状が悪化していく。望月家の人々と沢田の恋人(樋口可南子)は、それに同情を示して沢田の元を訪れるが、さらには望月家の子ども達にしきりに絡んでいた不良少女(荒井玉青)までが毎日沢田の家を訪問するようになる。沢田は、当初見せていた攻撃的な側面を見せなくなり、何だかしおらしくなって、ちょっとばかり拍子抜けである。そしてやがて収束に向かっていくという展開になる。例によって最後は大団円で終息するという結果になる。
望月家に騒動をもたらしている元カメラマン、沢田(山崎努)の病状が悪化していく。望月家の人々と沢田の恋人(樋口可南子)は、それに同情を示して沢田の元を訪れるが、さらには望月家の子ども達にしきりに絡んでいた不良少女(荒井玉青)までが毎日沢田の家を訪問するようになる。沢田は、当初見せていた攻撃的な側面を見せなくなり、何だかしおらしくなって、ちょっとばかり拍子抜けである。そしてやがて収束に向かっていくという展開になる。例によって最後は大団円で終息するという結果になる。
沢田が死の恐怖で弱みを見せるあたりはなかなか良い描写だが、最後に物わかりが良くなってしまうのは少々腑に落ちない。とは言うものの、破綻はなく整合性はとれている。
このドラマはなにしろ、それぞれの登場人物が非常にリアルで、性格もしっかり描きわけされていて、実在の人物のような存在感がある。こういったあたりが、このドラマの特質である。他人(血縁関係のあるものもあるが)同士が、お互いの生活に介入し合い、そこに人のぶつかり合いが生じてドラマが生まれる。この当時のドラマ、特に山田太一作品にはそういうものが多いが、それがごく自然に展開するため、違和感を感じることがない。このあたりが山田ドラマの大きな魅力であり、すごさなんだろうなと、このドラマを見ながらあらためて考えた。ただやはり最終回の展開は、どうにもいただけない感じがして、最後までモヤモヤが残った。
★★★☆
参考:
竹林軒出張所『「早春スケッチブック」、「夕暮れて」など(ドラマ)』
竹林軒出張所『時にはいっしょに(1)〜(11)(ドラマ)』
竹林軒出張所『沿線地図(1)〜(15)(ドラマ)』
『テレビがくれた夢 山田太一 その2(ドキュメンタリー)』
『山田太一のドラマ、マイベスト5』
2019年6月、記
上に戻る![]()
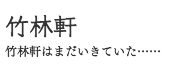
 ホーム
ホーム メール
メール





